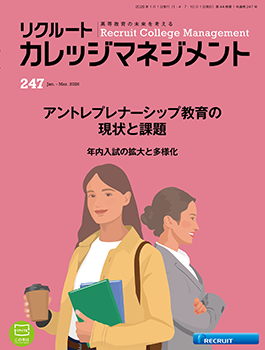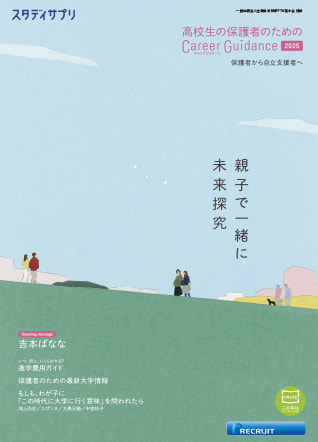Publication
刊行物
リクルート進学総研では、大学や専門学校の経営層の皆さま向けに『カレッジマネジメント』を、進路担当教員・校長・教頭・副校長、クラス担任、保護者に向けて『キャリアガイダンス』を発行。
全国の大学、短大、専門学校など、高等教育機関の経営層向けに発行している高等教育の専門誌。
政策動向やマーケットの最新情報、高等教育機関の事例などをお届けしています。年4回発行
カレッジマネジメント Vol.247 Jan.-Mar.2026
アントレプレナーシップ教育の現状と課題
編集長・小林浩が語る 特集の見どころ
アントレプレナーシップの意味や定義をしっかりと理解し、育成する人材像に合致した取り組みを
最近、「アントレプレナーシップ」という言葉をよく聞く。しかし、色々な方とお話しすると、その定義は非常に曖昧で、人によって受け取り方がバラバラな気がしている。ある大学では、アントレプレナーシップは起業家(アントレプレナー)を育成するもので、主体的に行動し、自ら事業を立ち上げることだと言う。そのために、ビジネスコンテストやピッチコンテストを開催し、産学官連携のプログラムに学生参加を促している。一方、ある大学ではアントレプレナーシップは、あくまで起業家精神であり、将来に向けて主体的に自らが考え行動できる教育の基盤だと言う。その大学では、起業家精神を醸成するためのコンピテンシーを定義し、全学的な教育プログラムの見直しを図ろうとしている。こうした状況を一度立ち止まって整理してみようということで、今回特集を組むことにした。
今回の特集を通じて気づいたのは、“entrepreneurship”はshipが示すように、「教え・練習し・観察して評価しうる資質・技能を含む概念である(馬場氏、冨田氏P.12)」ということである。さらに、アントレプレナーシップには世界的にも多義的に捉えられていて、広義と狭義の解釈が存在している。広義では自立して、創造的にイニシアチブを取って行動し起業家的な思考や行動特性を持つこと、狭義ではまさに起業家育成を意味するということである。広義と狭義の捉え方の混同により、教育内容や取り組みも混乱しているのが現状なのではないか。
そうしたなか、2025年春には文部科学省が「日本版EntreComp v1」を開発し、公表した。これは、EUが2016年に定めたEntreCompを参照にして日本向けに再設計したものである。Comp という言葉が示すように、アントレプレナーシップ醸成に向けて、どのようにコンピテンシーを伸ばしていくかを整理したものとなっている。初等教育から高等教育までを網羅していることから、アントレプレナーシップ教育とはどのように取り組んだらよいのかと考える際、大学のみに拘らず、小中高を持つ学校法人においても参考になるものである。文部科学省では、「全国アントレプレナーシップ人材育成プログラム」へと展開し、その浸透を図っている。
社会環境が大きく変化するなかで、次世代と担う若者たちに向けて、教育の在り方も、受け身の教育から主体的な学びへ、あるいはコンテンツベースからコンピテンシーベースへ、ということが言われ続けている。ではどうしたらよいのか、頭を悩ませている学校関係者も多いことだろう。2022年に導入された新学習指導要領では、学力の定義が見直され、学力の3要素という形で育成すべき資質・能力が定義し直された。それに基づいて、自ら問いを立て、解決への道筋を立てる探究学習が導入された。2025年には、新学習指導要領の一期生が大学に入学している。既にEntreCompを参考に、独自の教育プログラム構築に取り組んでいる大学も出てきている。こうした取り組みが浸透しつつあるなかで、各大学は育成する人材像を明確にしつつ、アントレプレナーシップをどのように位置づけ、育み、成果を出していくのか。各大学の取り組みに注目したい。
リクルート進学総研所長・リクルート『カレッジマネジメント』編集長 小林 浩
高校生の主体的な進路選択を応援する、進路担当教員・校長・教頭・副校長、クラス担任、保護者のための専門誌。
進路指導・キャリア教育に役立つ情報をお届けしています。年4回 (4・7・10・1月) 発行
キャリアガイダンス vol.457 2026.01
これからのコミュニケーションを紐解く
【Opening Message】「協働」の会話 × 吉田尚記(ニッポン放送アナウンサー)/高校生はコミュニケーションをどう捉えているのか/コミュニケーションの多面性を考える/社会で発揮されているコミュニケーションの形/多様なコミュニケーションの機会をデザインする高校事例
特集の見どころ
ここ10年間を切り取ってみても、コミュニケーションの手段や社会環境は大きく変化しました。オンラインでのコミュニケーションが拡大し、さらには生成AIの登場によって、伝達手段は過去に例を見ないほど多様化しています。働き方や生活様式の変化がコロナ禍によって急速に進み、さまざまなバックグラウンドをもつ人々との協働が、働く場における新しい規範となりつつあります。
このような環境下で、私たちはこれまでより複雑で多面的なコミュニケーションを求められています。もはや「コミュニケーション能力」は、画一的な正解や規範があるスキルとして一括りにすることが難しくなっているのではないでしょうか。
本特集では、高校生の声、大学や企業・組織の視点、社会で働く人、高校での取組を取材し、「これからのコミュニケーション」を紐解きます。
ぜひ、本特集を通じて、未来を生きる生徒たちに必要なコミュニケーションのあり方について一緒に考えていただけますと幸いです。