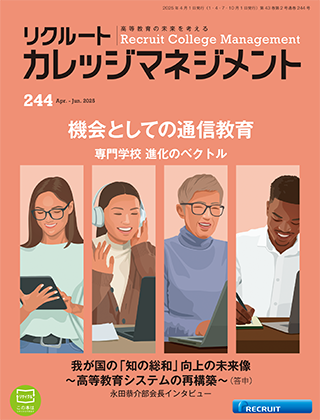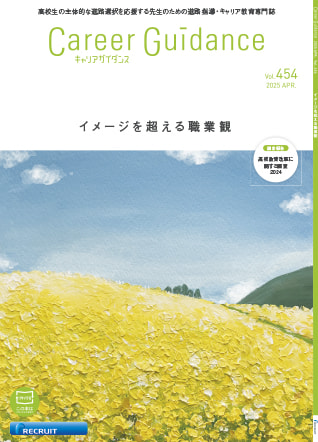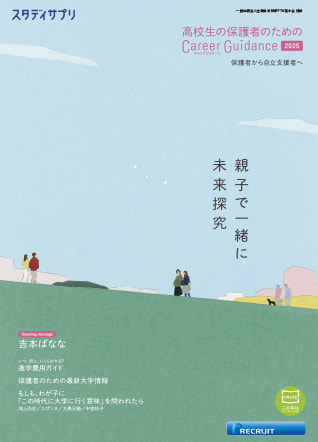Publication
刊行物
リクルート進学総研では、大学や専門学校の経営層の皆さま向けに『カレッジマネジメント』を、進路担当教員・校長・教頭・副校長、クラス担任、保護者に向けて『キャリアガイダンス』を発行。
全国の大学、短大、専門学校など、高等教育機関の経営層向けに発行している高等教育の専門誌。
政策動向やマーケットの最新情報、高等教育機関の事例などをお届けしています。年4回発行
カレッジマネジメント Vol.244 Apr.-Jun.2025
機会としての通信教育
編集長・小林浩が語る 特集の見どころ
社会人の学ぶ機会の広がりに加え、高卒者が学ぶ新たな場としての通信教育の可能性
これからの日本は、どの国も経験したことのない超少子化社会を迎える。2023年の出生数は73万人、2024年はまだ公表されていないものの70万人を切ると言われている。昨年11月に中央教育審議会で公表された最近のシミュレーションによると、2040年の大学全体の定員充足率は定員の約7割(72.75%)と予測されている。そこで注目されているのが、「国内」「18歳」「対面」といった伝統的ではない新たなマーケットである。その新たなマーケットを開拓する手段の一つとして有望視されているのが、通信教育である。
ITの発展とともに通信教育は進化しており、コロナ禍においてオンラインの活用がより一般化してきたことも市場拡大の大きな後押しとなっている。紙の教材で学び、添削とスクーリングという従来の形態から、完全オンラインという形態に大きく移り変わっている。大学の動向をみると、学部の社会人学生で伸びているのは、通学課程ではなく通信教育課程となっている。変化が激しい社会に対応するために、時間的制約があるなかでも、新たな知識や技術、教養の習得、あるいは資格取得を目指して、リカレントやリスキリングとして学ぼうとする社会人学生に通信教育課程が選ばれていることが分かる。大学がこれまで培ってきた特色や強みを通信教育として展開すれば、地域や年齢の制約なく、全国あるいは海外在住の日本人に対しても展開が可能となる。
また、高校では少子化が進み全体の生徒数は減少しているものの、通信教育課程、そのなかでも特に私立の生徒数が一貫して伸びている。通信制高校に通う生徒のインタビューを聞くと、近年は生徒像が変化しているのではないかと感じる。従来は、通学制課程に馴染めずに、通信制課程を選択する生徒が多かった印象がある。しかし、最近のインタビューでは、積極的に通信制課程を選ぶ生徒も増えているようだ。スポーツや芸能活動等、若いうちから自分自身のやりたいことを優先し、いつでもどこでも学べる通信制課程を選ぶ生徒。また、驚いたのは受験勉強に集中したいからと通学制から通信制に転校した、と語った生徒がいたことである。通学に馴染めないからではなく、積極的に通信教育課程を選択しているのである。学校基本調査から、通信教育課程の進学先を見ると、通学制の大学への進学が大半となっているが、これはこれまで受け皿がなかったことが要因とも考えられる。
2025年度の新設大学は2校、いずれも通信教育課程となっており、入学定員の合計は3850人となる。通信制学部の開設も増加している。これまでの大学の通信教育課程は社会人がメインターゲットだったが、新設大学や学部では高校生の出願も多くなっているそうだ。既存の大学にとっては、想像しなかった競合が表れた状況と言えるだろう。
拡大を続ける通信教育課程だが、課題もある。戦後、目的意識の明確な社会人が、働きながら学ぶためにスタートした通信教育課程。いつでも、どこでも、安価に、学ぶことができることが特徴である。そのため、質保証のあり方は、入口ではなく出口の質保証である。入学試験がなく、4年間という期間にとらわれず、厳しい単位認定を積み重ねて卒業する。入学試験はなく、4年間での卒業率は高くない。一方、今後は高校卒業から通信教育課程に直接入学する学生が増えていくことが想定される。いつでも、どこでも、安価で学べるというメリットは社会人と同様だが、あまり学ぶ目的意識が醸成されていない学生に対して、どのように厳しい単位認定を求めるのか、学びに向かうモチベーションを高めるためのサポート、学修支援体制は十分か。このような社会人とは異なる学生に対して、「質」をどのように担保していくのか。社会人とは異なる対応が必要になるかもしれない。
2014年に開設されたアメリカのミネルバ大学は全寮制の4年制大学だが、キャンパスを持たず、学生は世界7都市を移動しながら、各都市でプロジェクト学習を経験する。授業は全てオンラインだが、手厚いサポートで非常に高い評価を得ている。このミネルバ大学は、東京を学生が滞在する8拠点目とすることを発表している。そうなると、オンラインという手段でも高いレベルで学べるということが、当たり前と捉えられるようになる時代が到来する可能性がある。ただ、「第2のミネルバ大学」は現時点では出現しておらず、今後の動向が注目される。
リクルート進学総研所長・リクルート『カレッジマネジメント』編集長 小林 浩
高校生の主体的な進路選択を応援する、進路担当教員・校長・教頭・副校長、クラス担任、保護者のための専門誌。
進路指導・キャリア教育に役立つ情報をお届けしています。年4回 (4・7・10・1月) 発行
キャリアガイダンス vol.454 2025.04 NEW
イメージを超える職業観
【Opening Message】職業と私 × 魚住りえ(フリーアナウンサー、スピーチ・ボイスデザイナー)/あなたの仕事は何ですか?/「こういうもの」の枠を外して職業をとらえ直す/「自分」と「働く」を重ねる高校事例
特集の見どころ
数ある職業から自分がなりたいもの、自分に適したものを見つけるためには、自己を掘り下げると同時に、世の中にはどのような職業があり、日々どのような仕事をしてどのような価値を生み出しているのかを知ることが不可欠です。
一方、SNSやインターネットでの情報収集が当たり前になった現代では、職業に対しても一面的な情報から「知ったつもり」になりがちです。特に、まだ社会との接点が少ない高校生は、職業に対する漠然としたイメージや固定観念に縛られ、進路の選択肢を狭めてしまうこともあるでしょう。また、急速に社会が変化するなか、新しく生まれた職業や、従来とは仕事の内容や働き方が変わりつつある職業も出てきています。
そこで今号では、職業に対する思い込みを外し、働くことや自分の進路に対して想像力を広げるにはどうすればいいのか、多角的にアプローチします。本特集の視点が、進路指導やキャリア教育の一助になれば幸いです。