大学が目指す方向性と現場の思いを尊重した入試方式の調整に尽力
2025/11/25

「その一歩が、大学を変える。」
日々の業務のなかにある工夫や挑戦。同じフィールドで奮闘する職員達のリアルなストーリーから、あなたの“次の一手”が見えてくるかもしれません。
「Next up」は、大学の未来を担う私達自身の知恵と経験をつなぎ、広げるための企画です。
氏名:小牧 涼(こまき りょう)氏
大学名:東洋大学
所属部署:学長室学長事務課
大学卒業後、2017年4月に東洋大学に入職。8年2カ月の間、教務部文学部教務課に勤務し、主に教務関連業務を担当。2025年6月に学長室学長事務課に異動。主に教学予算を担当するユニットにて、各学部の教育に係る予算管理に関わる。参考にしている情報源は私大連発行の『大学時報』。
【サクセスエピソード】
入試方式が拡大する中での円滑な関係各所との調整
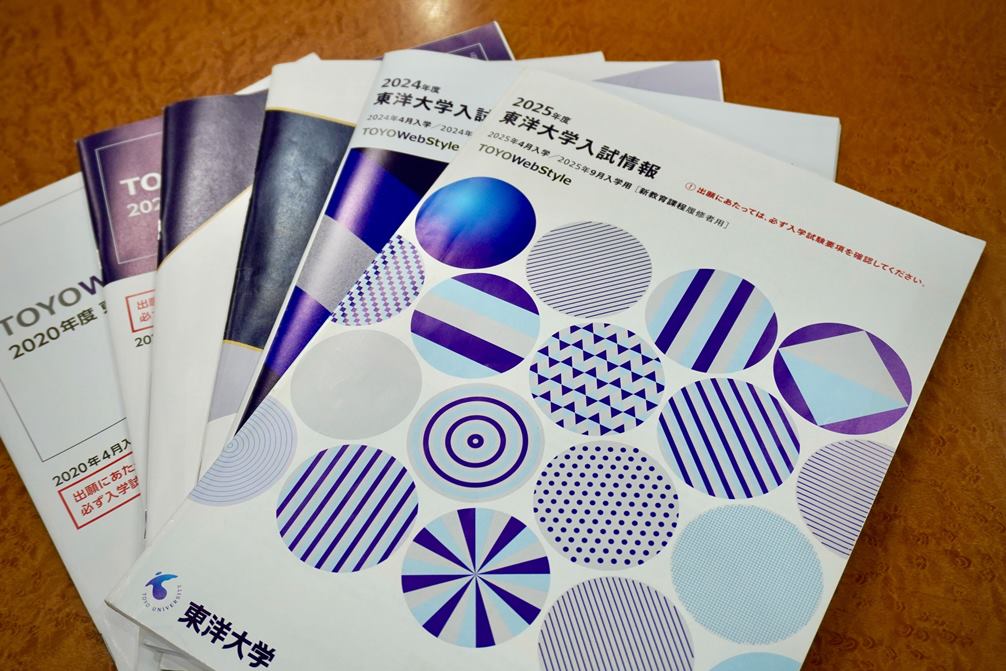
これまでの経験を振り返り「自分の成功体験だ」と言えるのは、教務部での8年間、学部の入試業務を毎年滞りなく進めて来られたことです。
入試業務とは、私が担当していた文学部における各学科の入試方式の検討から実施、合否策定までの一連の業務を指しますが、特に学部教務の職員として入試部や各学科の教員と協働しながら、毎年の入試方式について調整を続けてきた経験は、自身の糧となっています。
立案にあたっては、例年入試部から次年度の入試方式について提案を受け、その内容をもとに各学科の先生方との擦り合わせを行いながら最終判断を行います。学科にもそれぞれ抱えている目標や課題、求める学生像などがあるため、まずは提案事項の意図や効果などを教務部の職員が把握した上で、学科の先生方に丁寧に情報共有を行い、双方の思いを尊重しつつ時には落としどころを探りながら、効果的な入試方式を設定できるよう努めていました。
文学部は本学の中でも学科数が7学科と最も多く、かつ入試改革に伴い入試方式が年々変化しているため、情報を丁寧に整理しつつできるだけ迅速に調整を進めていく必要があります。特に2025年度の文学部の入試では、前年度比で入試方式数が大幅に増加し、一般選抜だけでも学部全体で200を超える方式数となったことから、精度を求めつつもかなりタイトなスケジュールでの作業が求められました。限られた時間と人数の中で、入試部、教務部、各学科の考えを細やかに擦り合わせる作業は簡単なものではありませんでしたが、こまめな情報共有などを重ねて関係各所との協力体制を整えることで、円滑な業務遂行を実現することができました。
【私の仕事術】
相手を理解した上で誠実にコミュニケーションを取る
どのような立場の人に対しても、まずは相手のことを理解し、相手がどう受け取るのかを考えたうえで、誠実かつ丁寧なコミュニケーションを行うことを心掛けています。部署や立場が違っても最終的には「人と人」との関わりで仕事を進めていくことになるため、相手の思いや感情にも配慮しつつ、自身の思いを伝えるようにしています。
ただ、その際に根拠がないまま思いを伝えても、良い意見交換にはならないので、データなど判断材料となり得る情報を提示するなどして、論点を明確にすることを心掛けています。例えば入試業務の調整においては、入試方式を変更したことで受験者数はどう変化したのか、入学後の学力や成績はどう変化しているのか等の客観的な情報もできるだけ詳細に共有することを大切にしていました。
【今後の展望】
大学全体が一丸となって同じ方向に歩めるよう尽力したい
2025年6月に学長室学長事務課に異動になり、現在は学内の全学部の教学予算管理に関わっています。これまでは文学部の現場のみを見ることのほうが多かったのですが、今の業務ではすべての学部の教職員との関わりが増えたため、これまでとは視座が変わり、大学全体を俯瞰して見られるようになりました。その一方で、役割や立ち位置は変わりましたが、教務部時代と同様、丁寧な情報共有とコミュニケーションを大切にしたいという気持ちには変わりありません。学長が掲げる方針のもと、大学全体が同じ方向に向かって教育・研究活動を進めていけるような、そのための潤滑油的な存在を目指したいと考えています。
全国の若手職員の皆さんも、所属する大学をより良くするため日々尽力されていることと思います。変動の激しい世の中ですが、そんな中だからこそ、教職員同士の積極的なコミュニケーションが大切だと実感しています。大学が良い方向に向かっていくためには何が必要なのか、経験や知識に基づく自分の意見をしっかり持ったうえで意見交換を重ねることで、新たな打ち手やアイデアが見えてくるはず。コミュニケーションを通じて自分にはない意見も取り入れながら、常に多角的に物事を捉え続けることが、これからの大学職員に求められる要素の一つではないかと思います。

(文/伊藤理子)
