教えて!「教科書の扱いは今後どうなるの??」
今年度に採択される教科書の展示会が行われています(6月14日から7月31日までの任意の14日間を中心に開催、地域によって日程は異なる)。年々カラフルで丁寧な教科書が増えているのは結構ですが、各高校では生徒の多様化が進み、1種類の教科書だけでは対応しにくくなっている実感も募ります。デジタル教科書の普及動向も気になります。今後の教科書は、どうなっていくのでしょうか。
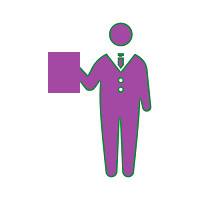
10日、文部科学省内で注目される動きがありました。「今後の教育課程、学習指導及び学習評価等の在り方に関する有識者検討会」の第12回会合 で「教科書・教材の在り方について」が議題の一つに上がったのです。
これに関して発表したのは、かつて中央教育審議会の初等中等教育分科会長や教育課程部会長も歴任した天笠 茂座長(千葉大学名誉教授)。小中学校に限っての話でしたが、最近の教科書は若手や指導力が十分でない教師を前提に編集されているため 、指導力育成につながらない恐れがあると指摘。これから教科書が変わっていくポイントとして ▽児童生徒の個別ニーズに対応した多様なアプローチ ▽弾力的な時間割への対応 ▽問題解決に向かう途中での思考・判断・表現をより重視しつつ、結果として理解や知識・方法の習得につながる在り方 ▽記載すべき知識の量や発展的内容の在り方――を挙げました。
もう一つの議題「各教科の目標・内容の示し方について」で発表した奈須正裕座長代理(上智大学教授)や石井英真委員(京都大学大学院准教授)も、教科書が「指導書化」していることなどを問題視。在り方を問い直すよう訴えました。
同検討会は、おおむね10年に1度とされる学習指導要領の次期改訂に向けた論点整理を目指しています。現行指導要領の審議過程でも同様の検討会が設置され、教育課程だけでなく指導方法や学習評価までを一体的に検討し、高校で観点別評価が本格的に導入される流れも作りました。次期改訂では、教科書・教材についても踏み込んで審議が行われそうな気配が濃厚です。
背景には、GIGAスクール構想の実現で1人1台のICT(情報通信技術)端末が当たり前になったことがあります。学校現場には2021年1月の中教審答申に基づき「個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実」も求められていますが、端末をフル活用すれば必ずしも一斉授業にとらわれる必要はなくなり、一つの教室内で各自やグループの進度に応じてバラバラに個別最適な学びや協働的な学びが行える可能性も広がっています。
次期指導要領は、そうした「教育DX(デジタルトランスフォーメーション=デジタルによる変革)」下で初の改訂になります。21日に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針(骨太の方針)2024 」にも「柔軟な教育課程の実現に向けた取組」が盛り込まれました。授業の変革に合わせて、教科書の在り方も問われることになるというわけです。
もちろん「主たる教材」としての役割が変わったり、検定教科書の使用義務がなくなったりするわけではないでしょう。昔から「授業では教科書
そんな時代を前にして、そのまま授業で使いやすかったり、より大学受験に対応していたりする教科書をいつまでも選ぼうとしていては本末転倒です。今こそ「やりたい授業」(奈須座長代理)を第一にした教科書の在り方、選び方を考えたいものです。
【profile】
渡辺敦司(わたなべ・あつし)●1964年北海道生まれ。1990年横浜国立大学教育学部教育学科卒業。同年日本教育新聞社入社、編集局記者として文部省、進路指導・高校教育改革など担当。98年よりフリーの教育ジャーナリスト。教育専門誌を中心に、教育行政から実践まで幅広く取材・執筆。近刊に『学習指導要領「次期改訂」をどうする―検証 教育課程改革―』(ジダイ社)。
教育ジャーナリスト渡辺敦司の一人社説 http://ejwatanabe.cocolog-nifty.com/blog/




