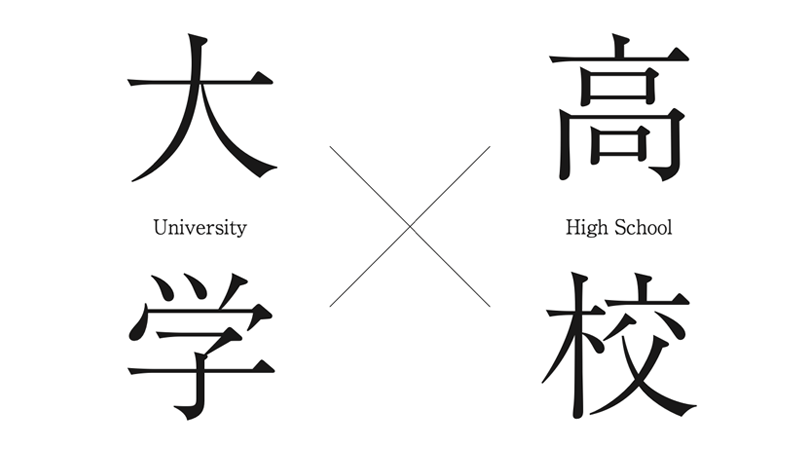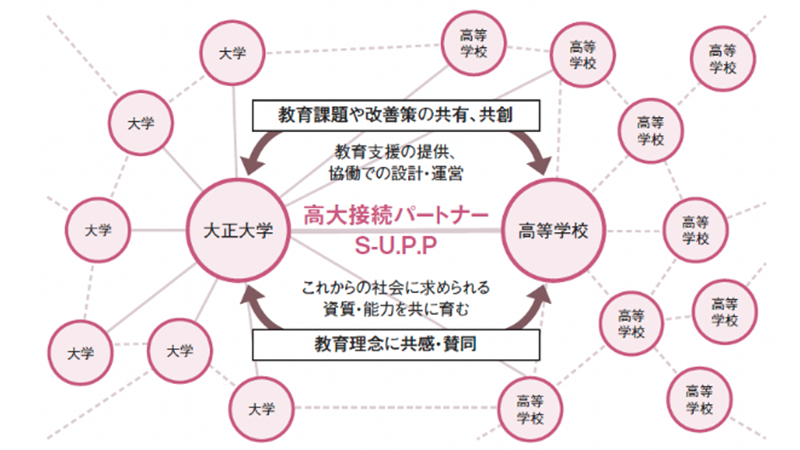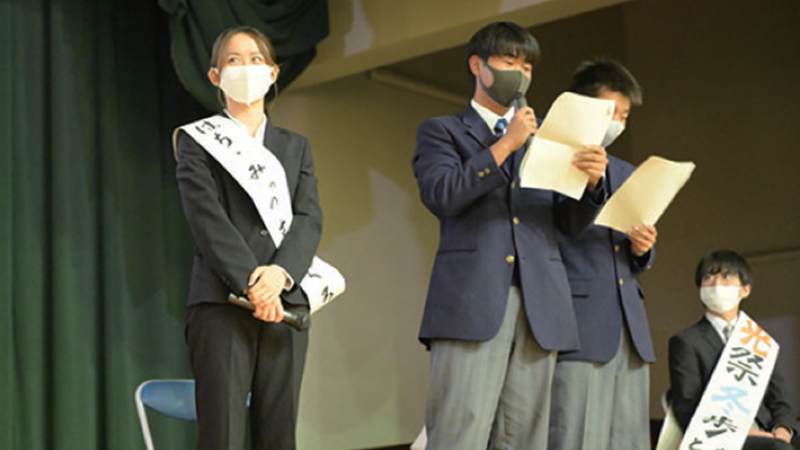【第2回 努力のプロセス、その言語化とは】
藤岡慎二(産業能率大学経営学部教授 兼(株)Prima Pinguino 代表)
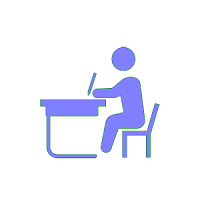
1.前回まで
With コロナ時代の新しい生活様式における推薦・AO入試で何が起きるのか、どう向き合うかについて言及して来ました。①大会、コンクール、展覧会が延期・中止により出願書類や志望理由書、面接などでPRする実績を積むことができない。
②休校期間中に生徒を指導できず、対策が遅れる。
③地域連携や生徒たちの主体的な活動などができず、学びを深められない。
このような状況において、大学側は高校生自身のコンピテンシーを評価します。コンピテンシーとは思考特性・⾏動特性、そしてその背後にある価値観や信念です。それが、⼤学側がみたい「⼈となり」で、その高校生が大学入学後に活躍するだろうと期待感を持ち、評価をするという話をしてきました。
今回は、令和3年度大学入学選抜実施要項に記載された「努力のプロセス」をどう理解すればよいか、言語化が期待感と評価にどう繋がり、いかに言語化すれば良いのか。今回は、その内容についてお伝えしようと思います。
2. 令和3年度の総合型選抜・学校推薦型選抜の変更点
6/19に令和3年度大学入学者選抜実施要項について、文部科学省から発表がありました。推薦・AO入試対策に関係するのは以下の2点です。(1)試験の実施日
・総合型選抜(旧AO入試)は出願開始が8月1日から9月15日に。
・学校推薦型選抜(旧推薦入試)は11月1日から出願開始。(変更なし)
(2)中止・延期等となった大会や資格・検定試験等への対応
総合型選抜及び学校推薦型選抜においては,以下のような選抜の工夫に配慮する。
(ア) 評価の方法や重み付け等に配慮し,この間の個々の入学志願者の成果獲得に向けた努力のプロセスや入学を志願する大学で学ぼうとする意欲を多面的・総合的に評価するものとする。このため,各大学は,入学志願者の実情に配慮した丁寧な選抜を行う観点から,推薦書,志願者本人が記載する資料においてこれらの努力のプロセス等について記載を求めることなど評価方法を定め,その内容を募集要項等で周知するものとする。
特に「成果獲得に向けた努力のプロセスや入学を志願する大学で学ぼうとする意欲を多面的・総合的に評価する」がポイントになりそうです。
3.努力のプロセスとは何か?
努力のプロセスとは、「受験生が懸命に取り組んだ活動での障害や困難に対する価値観や思考、行動」のことと言えるでしょう。なぜ、努力のプロセスが重要なのでしょうか。大学は、努力のプロセスにより、受験生の「人となり」を理解できます。なぜなら、「人となり」は障害や困難に立ち向かう時にこそ、表出化するからです。人間の本性は困難に立ち向かう時に明らかになるからなのです。4.努力のプロセス(経験)の言語化
努力のプロセス(経験)を言語化できなければそもそも、大学には評価されませんので、言語化する力は重要だとわかります。さらに言語化できる能力は、本人のポテンシャルの可能性を示します。困難に立ち向かったとき、如何なる価値観と思考、行動がうまく物事を運ぶのか。物事がうまくいかない、失敗してしまう時は、どのような価値観や思考、行動で取り組んだ時なのか、を言語化します。すると、言語化により、うまく物事を運ぶことを何度も再現でき、失敗を回避することができるようになります。結果、受験生本人のパフォーマンスは向上しますし、今後は高い成果を期待できるわけです。つまり、経験を言語化できると、大学に、受験生の人となりや能力をPRするだけではなく、大学への期待感を醸成することができるのです。5.経験を言語化する手法〜STAR法〜
経験を言語化し、相手に自分自身の個性を伝える手法として、STAR法があります。STAR法では【Situation】:どのような状況(時・場所・登場人物・起きていること)だったのか
【Task】:どのような課題・困難・障害があったのか
【Action】:それをどのように乗り越えたのか、考えたのか
【Result】:その結果得たこと、気づいたことは何か
それぞれの項目の問いに答えれば、自身の経験、努力のプロセスを言語化することができます。特に「成果獲得に向けた努力をしていた状況」について、STAR法で言語化することができれば、例え、展覧会・コンクール・大会での実績や成績が無くとも、成果獲得に向けた努力のプロセスが示せるのです。特にActionとResultがポイントです。Actionでは、その状況における困難に立ち向かう価値観と思考、行動を記述し、Resultでは結果と気づいたことを記述すれば「人となり」を志望校にPRすることができます。
事例を出してみましょう。
【Situation】:私が通う高校の英語学習では、英語の先生の方針で英語での読み書き以外にも、英語での会話が授業中に頻繁に行われていた。英語は英語で学ぶという信念を持った先生だった。
【Task】:英語での会話は、自身の考えを言葉にした上で、英語に変え、相手にわかりやすく伝え、更に相手の英語での発言を聞き取らなければならない。今までにない経験に私は戸惑った。
頭に浮かんでも口に出ないもどかしさや、悔しさが私を何度もくじけさせそうだった。
【Action】:しかし、ピンチはチャンスだと思った。英語が話せるようになれば世界を股にかけて働けるようになる、より多くの人たちと話をして世界中の様々な異文化や事柄について理解できると信じ、授業外で工夫をすることにした。仲の良い友人との何気ないメールのやり取りを少しずつ英語にしてみたのだ。すると、いつもよりも積極的に英単語や表現、文の組み立て方を意識し、自ら進んで学ぶことができた。
【Result】:結果的に英語での会話だけでなく、英語全体の成績も上がった。自身の興味や日常生活をきっかけとした学びは、主体性や積極性を生むことに気づいた。その後は英語以外の科目でも自身の興味や日常生活をきっかけとすることが積極的に学ぶ秘訣だと気づいた。また英語で学ぶことの大切さ、つまり英語を目的として学ぶのではなく、手段として学ぶ。今までの学び方では、限られた人にしか効果は出ない。自らの学びは自ら考えることが大切であると意識するようになった。
以上がコロナ禍時代の推薦・AO入試において実績や成績に代わり、評価される「努力のプロセス」を言語化する方法です。しかし、これはコロナ禍に限ったことでは無く、いつの時代でも普遍的なことなのではないかと思うのです。
<参考>
【文部科学省】2002.6.19令和3年度大学入学選抜実施要項
【大学入試センター】2020.6.30令和3年度大学入学者選抜に係る大学入学共通テスト実施要項
→前の記事【第1回 大会、コンクール、展覧会などでの実績・成績は必須なのか?】