キャリアガイダンス vol.425 2018.12
「探究」で育む
資質・能力とその評価
探究の問いをどう“自分ごと化”していくか?/生徒が自ら伸びていく「探究」をどう仕掛けるか/探究の仕掛けをドライブする ツール&リソース/探究をどう捉え、どのような評価観をもつべきか/探究活動の評価を模索した20年/質の高い問題解決者を育てるために/「探究」のあるこれからの学校
編集長が語る 特集の見どころ
「アクションを気にしすぎて自分の好きなようにできなかった」「私の班は大船渡も大船渡ではない所も学べてない気がする…。今思っていることは堤防なんて調べなきゃよかった」。「大船渡学」で探究学習に取り組む生徒たちの振り返りのコメントの一部です。
皆さんは何を感じるでしょうか?
新しい学習指導要領において、高校は「総合的な探究の時間」へと進化しました。なぜ高校だけが変わったのでしょうか?そこに込められたメッセージとは何でしょうか?
新旧学習指導要領の比較を通した理解に加え、学習者の視点に立ち、中学・高校を通じた学びの縦の連続線で捉えてみることで浮かびあがるテーマがあるように思います。
生徒のキャリア発達段階に応じて、特に高校生ともなれば、設定する探究テーマは自己の在り方生き方と大きく関わっていくもの。課題と自身との関係で何度も繰り返し捉え続けていくことが求められます。
しかしながら、自ら問いを立てることは決して容易ではないことは、先生方も実感のあることだと思います。どうしてそれが気になるのか?〝活動あって学びなし〞ではなく、本物に触れ、本気で知りたい、自分がなんとかしたいと思えるかどうか。問いが〝自分ごと化〞した生徒たちの学びは、教員の予測を超えて、深く広がりを見せていくのではないでしょうか。
探究を通じて育んでいく資質・能力とは?問いをどう立て、磨くのか。そして探究活動の評価をどう考えればいいのか?
人生が問題解決の連続であるとすれば、探究に取り組むことが、生徒ひとり一人のキャリアを切り拓く糧となるはずだと思っています。だからこそ今、すべての学校で探究モードへ。前号に続き、本特集がお役に立てれば幸いです。
山下 真司(本誌 編集長)
■特集■
「探究」で育む 資質・能力とその評価
探究の問いをどう“自分ごと化”していくか?
大船渡高校(岩手・県立)
生徒が自ら伸びていく「探究」をどう仕掛けるか
佐野和之 (東京・私立かえつ有明中・高校)
山藤旅聞 (東京・都立武蔵高校・附属中学校)
廣瀬志保 (山梨・県立吉田高校)
野口 徹 (山形大学学術研究院 教授)
生徒を学びの「主役」にするため
すべての高校で、今こそ”探究モード”へ
野口 徹 (山形大学 学術研究院 教授)
探究の仕掛けをドライブする ツール&リソース
探究をどう捉え、どのような評価観をもつべきか
西岡加名恵 (京都大学大学院教育学研究科 教授)
探究活動の評価を模索した20年
堀川高校(京都・市立)
質の高い問題解決者を育てるために
奈須正裕 (上智大学総合人間科学部 教授)
「探究」のあるこれからの学校
松井孝夫 (群馬・県立中央中等教育学校)
三浦隆志 (岡山・県立林野高校)
■連載
進路指導実践を磨く!
聖霊中学校・高校 (愛知・私立)
進路指導ケーススタディ
第8回 保護者との面談を、どう進めるか?
地域課題解決型キャリア教育
須崎高校 (高知・県立)
教科でキャリア教育『国語』
筧 美和子先生 春日部女子高校(埼玉・県立)
『希望の道標』
第48回:ONE JAPAN共同発起人・代表/濵松 誠
今、教育が変わるとき。 LEADERS
実践女子学園中学校高校 校長 髙橋基之
初芝富田林中学校・高校 校長 平井正朗
Top Interview -変革に挑む-
津田塾大学 学長 髙橋裕子
学校法人 電波学園 理事長 小川明治
リクルートサービスを活用した進路指導実践事例
【進路】日根野高校 (大阪・府立)
【学習】中央大学杉並高校 (東京・私立)
■別冊付録
学校現場は「主体性」「協働性」を
どこまで育てているか?
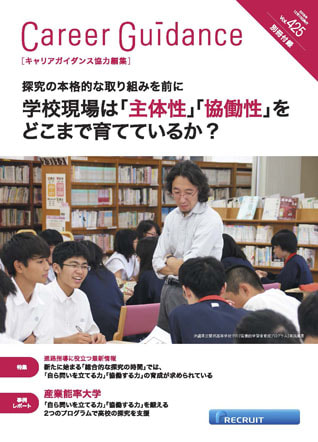
新たに始まる「総合的な探究の時間」では、
「自ら問いを立てる力」「協働する力」の育成が求められている
事例レポート:産業能率大学
「自ら問いを立てる力」「協働する力」を鍛える
2つのプログラムで高校の探究を支援

