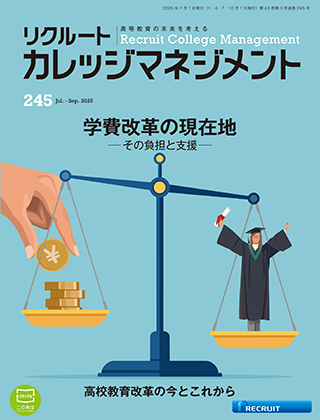カレッジマネジメント Vol.245 Jul.-Sep.2025
学費改革の現在地 ― その負担と支援 ―
編集長・小林浩が語る 特集の見どころ
少子化時代の学費負担、3つの視点から考える
昨年来、東京大学の授業料値上げを発端として、大学の学費が話題となっている。学費を考えるに当たって、大きく3つの視点から整理してみたい。
1つは学費を「負担」する側の視点である。学費を負担する側の家庭の状況を見ると、名目賃金は上昇する一方、賃金上昇を上回る物価上昇が生じており、家庭の学費への負担感は高まっているようだ。
大学進学率は約6割に達しており、これまで大学に行っていなかった層の大学進学者が増えていることも背景にあると思われる。本特集のリベルタス・コンサルティング 八田 誠氏のリポートから抜粋すると、夫婦と子ども二人、うち長子が大学生の世帯では消費支出のうち26.4%が教育関連支出(2019年全国家計構造調査)となっており、2022年度の独立行政法人日本学生支援機構(JASSO)の調査では、大学学部生(昼間部)の55%が奨学金を利用しているとのことである。その結果、2023年度の文部科学省の意識調査※1では、なんと6割が大学等の教育費が負担であり、少子化の要因となっていると回答している。
2つ目の視点は学費を「決める」側の視点である。物価上昇は、当然家庭だけではなく、大学にも及んでいる。光熱費等の諸費用の高騰、設備施設の老朽化への対応、人件費の上昇等をどのように吸収するかは、経営上の大きな課題である。コスト増を吸収できなければ、教育・研究の質に影響が出てしまう。企業であれば、需要と供給のバランスや市場競争力によって商品・サービスの価格は決まってくる。しかし、大学は「公器」としての役割があるため、コスト増を直接学費に反映することが難しい。加えて、国等からの補助金を得ていること、国立・公立・私立といった設置者において事情が異なることから、学費の算定根拠が一般家庭から見ると分かりづらい点もやっかいだ。私立大学は学納金が収入の約8割を占めており、学費の決定は大きな課題である。
そこで3つ目の視点、学費の「支援」である。この支援の拡充による学費負担の軽減が、昨今の新たな動向を把握するポイントとなりそうである。まず、国による支援として、高等教育へのアクセス強化を目的とする修学支援制度が導入され、対象が拡充されている。次に、大学独自の奨学金である。これは、学費自体は必要コストを吸収して上昇するものの、各大学の理念やビジョン・ミッションに合致した学生の獲得に向け、戦略的に給付型の奨学金を支給するような、「高授業料/高奨学金政策(桜美林大学 小林雅之特任教授)」が拡大していると考えられる。
これに加えて、自治体や企業からの支援が増加している。少子化の流れの中で、若者の人口流出は地域の大きな課題だ。各自治体が奨学金等を設けるケースが増えてきている。また、少子化の中で、企業の人材確保も重要な課題となっている。2025年の大学卒の採用計画を充足できた企業は、全体の37%に留まっている※2。2021年より企業が従業員の奨学金を代理で返還する国の制度が始まったこともあり、2024年度には代理返済の導入企業は3266社に増え、支援対象者も1万人を超えたという(JASSO)。支援の輪は一つではなくなってきており、拡がりを見せている。
2024年2月にまとめられた答申、『我が国の「知の総和」向上の未来像 ~高等教育システムの再構築~』では、高等教育のアクセス確保の方策として、「経済的支援の充実」を掲げている。また、高等教育改革を支える支援方策のあり方として、「公財政支援、社会からの投資等、個人・保護者負担について持続可能な発展に資するような規模・仕組みを確保する」とも記されている。その一方で、高等教育機関の必要コストの算出、明確化も打ち出している。人口減少が進む中で、一人ひとりの資質能力を高めていくことは、重要課題である。その中で、公器ともいえる大学の学費を誰が負担するのか、これから大きな議論になっていくことが想定される。既に、大学院修士課程や専門職学位課程では、在学中は授業料を納付せず、卒業後の所得等に応じて納付できるという授業料後払い制度が始まっている。
様々な支援制度が導入され、経済的に厳しい状況にある学生が、進学できる制度が充実するのは大歓迎である。その一方で、前述の文科省の意識調査※1では、修学支援新制度の認知率はわずか15.1%に留まっているとのことだ。せっかく支援制度が拡充されても活用されなければ意味がない。分かりやすい制度設計を構築するとともに、対象となる学生や家庭にどのように浸透させていくかが、今後の重要な課題と言えるだろう。
- 令和5年度文部科学省委託「高等教育の教育費負担等に関する調査研究」
- リクルート就職みらい研究所「就職白書2025」
リクルート進学総研所長・リクルート『カレッジマネジメント』編集長 小林 浩
■第1特集
学費改革の現在地 ― その負担と支援 ―
Report
高等教育費の負担のあり方及び負担軽減策の認知度に関する意識等
八田 誠 株式会社リベルタス・コンサルティング
Contribution
大学の学費無償化に関する課題と解決の方向性
小林雅之 桜美林大学 特任教授
Case Studies
全学的戦略の実現に奨学金を活用する大学
芝浦工業大学
長期ビジョンにダイバーシティの推進を掲げ、目標達成に独自奨学金を活用
金沢工業大学
外部資金による教育投資とコーオプ教育で実現する学費を「上げない」学費戦略
Report
「企業等の奨学金返還支援(代理返還)制度」の現状と課題
日本学生支援機構(JASSO)に聞く制度の概要と目的
松屋フーズ
リンクアンドモチベーション
Contribution
地方公共団体による奨学金返還支援の取組等について
塩田剛志 内閣官房新しい地方経済・生活環境創生本部事務局/内閣府地方創生推進室 参事官
■第2特集
高校教育改革の今とこれから
Research
新学習指導要領のもと、教育改革を進める高校現場の教員と生徒の現状
調査報告 高校教育改革に関する調査2024
Case Studies
教育改革が進む普通科高校の現状
岩手県立大槌高等学校
多様な進路意向に応えるカリキュラムと地域と連携した探究的な学びにより一人ひとりの強みを育てる
福岡県立八幡高等学校
「行ける高校」から「行きたい高校」へ。主体的に考え行動する「自走力」のある生徒を育てる
島根県私立明誠高等学校
地域・社会との関わりを通じて生徒の主体性・自律性を育てる手段としてメタバースの活用を模索
Interview
初等中等教育の教育改革を振り返る
田村 学 文部科学省初等中等教育局 主任視学官
--------------------
■連載
データで見る高校生の今
TOP INTERVIEW
入試は社会へのメッセージ
#14 桜美林大学
高大接続事業「ディスカバ!」と「探究入試Spiral」の今
リカレント教育最前線
#11 星槎大学 『 学生支援のためのスクーリングサポートブック(教職員用)』
「地域人材育成」のため全国各地の自治体・企業との連携を強化。目指すは全47都道府県への大学院設置
学ぶと働くをつなぐ
#48 鳥取短期大学
地域の経済団体が支援、「地域から信頼され、頼りにされる短大」に
松村直樹
大学を強くする「大学経営改革」
#106 会議運営と文書作成から大学の仕事を問い直す
吉武博通