【寄稿】地方公共団体による奨学金返還支援の取組等について/内閣官房新しい地方経済・生活環境創生本部事務局/ 内閣府地方創生推進室 参事官 塩田剛志
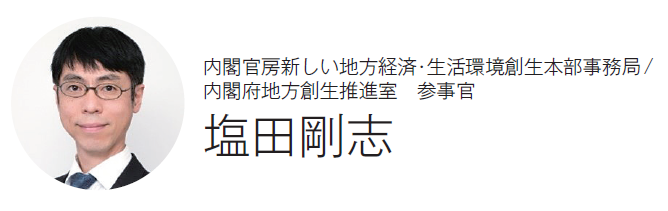
【1】地方公共団体による奨学金返還支援実施の背景、狙い
地方公共団体による若者への奨学金返還支援は、域内企業等への就職を促し、地方への定着を推進する施策として、地方公共団体が独自に取り組みを進めてきたものである。地方公共団体では、団体ごとに定めた一定の要件(域内に一定期間居住、特定の業種に一定期間就業等)を満たす者に対して、奨学金返還支援を行っている。
地方創生の気運の高まりのなか、平成26年に策定された「まち・ひと・しごと創生総合戦略」において、「地方の若い世代が大学等の入学時と卒業時に東京圏へ流出している。(中略)地元企業への就職や都市部の大学等から地方企業への就職を促進するため、奨学金を活用した大学生等の地元定着」を推進するとして、政府としても、奨学金を活用した若者の地方定着を推進する旨が記載された。同戦略を踏まえ、関係省庁が連携し、地方公共団体が行う奨学金返還支援の取り組みを促進している。具体的には、総務省が、地方公共団体への財政措置として、奨学金返還支援に要した経費を特別交付税措置の対象とするとともに、内閣官房新しい地方経済・生活環境創生本部事務局において、全国の地方公共団体における奨学金返還支援の取り組み状況を毎年調査し、好事例とともに公表することを通じて、返還支援の取り組みの活用を促進している。
【2】実施状況
令和6年度調査(令和6年6月現在)によると、奨学金返還支援の取り組みを実施している地方公共団体は、47都道府県・816市区町村(令和5年度調査:42都道府県・717市区町村)であり、全ての都道府県と約5割の市区町村に、奨学金返還支援の取り組みが広がっている。
また、地方公共団体が令和5年度に返還支援を行った人数は2万6084人であり、そのうち、当該年度から新たに返還支援を開始した人数は1万1859人となっている。また、地方公共団体による支援実績総額は、約73.8億円である。
【3】奨学金返還支援の要件、支援内容等
地方公共団体による奨学金返還支援の具体的な要件は、団体ごとに定められているが、当該自治体内で一定期間の居住・就業を求めることが多い。就業先については、対象となる産業分野や企業を定めている場合や、医師、教員、保育士といった特定の職種に限定している場合もある。支援内容については、返還額の2分の1、3分の1といった一定割合について上限付きで支援する場合や、上限額のみ設定する場合がある。
また、地方公共団体に対する特別交付税措置の概要は以下の通りである。
【都道府県の場合】
- 奨学金返還支援のため地元産業界等との間で基金を設置した場合等に、都道府県の基金への出捐額、 広報経費に対して特別交付税措置
- 対象者の要件は大学等を卒業後に当該都道府県で就職すること等(都道府県と地元産業界等が合意して要件を決定)
【市町村の場合】
- 奨学金返還支援に係る市町村の負担額(基金の設置は不要)、広報経費に対して特別交付税措置
- 対象者の要件は大学・高校等を卒業後に当該地域に居住すること等
返還支援の対象となる奨学金については、地方公共団体自らが貸与する奨学金の場合と日本学生支援機構等が貸与する奨学金の場合がある。また、地方公共団体が個人に返還支援を行うのではなく、企業が従業員の奨学金の返還支援(代理返還)を行う場合に、地方公共団体が企業に支援を行う場合がある。この点に着目して、傾向を分析する。
①地方公共団体自らが貸与する奨学金についての返還の減免
地方定着を目的として、地方公共団体が貸与する奨学金について、卒業後も同一域内で一定期間就業・居住すること等を要件に、返還を減額・免除するもの。事例として多いのは、医師や看護師、薬剤師等の医療職を目指す学生の修学費用を支援する奨学金において、卒業後、資格を取得し域内の医療機関等にて一定期間勤務することで、返還を減額・免除する制度である。医療職のほかにも、保育士や介護士、教員等の職種で導入されていることも多く、不足している業種の人材確保の手段として有効活用されている。また、奨学金を活用する人にとっても返還に関する不安の減少につながっている。
②日本学生支援機構(JASSO)等が貸与する奨学金についての返還支援
日本学生支援機構等からの奨学金について、域内に就業・居住した場合に、地方公共団体が、返還金を支援するもの。支援内容は地方公共団体によって様々であるが、①では、一定期間の就業・居住後に減免が行われることが一般的である一方、②では、就業・居住した同一年度から支援を行う場合も一定割合ある。実際に、同一年度から支援を受けられる制度を活用した人からは、「奨学金を早期に返還するための無理のない計画を立てることができた」「経済的・精神的な不安感の解消につながった」等の声が聞かれている。地方公共団体は、他地域の大学等で学ぶ人に対するUIJターン促進のPRポイントとして有効活用している。
③企業が従業員の奨学金の返還支援(代理返還)を行う場合についての企業支援
企業が従業員の奨学金の返還を支援する場合、地方公共団体が当該企業に対して経費の一部を補助する取り組みである。この取り組みの特長として、企業が採用活動時に福利厚生の一つとしてPRできること、また、企業と地方公共団体で実施するため両者の負担が軽減されることがあげられる。特に新卒者の雇用に苦慮する中小企業にとって、奨学金返還支援は大きなPR ポイントとなり、「就職説明会等で企業PRがしやすく、雇用につながりやすい」「離職率が減少し、若手従業員の定着に一定の効果が見られた」「福利厚生項目が増え企業イメージが良くなった」という声が聞かれている。2021年より、企業から日本学生支援機構へ直接送金することが可能となり、法人税等で有利な扱いになりうるため、取り組み企業数が増加し、令和6年10月末時点で、全国で2587社が奨学金返還支援(代理返還)制度を利用している。こうした取り組みに合わせて地方公共団体として支援する事例も増加している。
【4】具体的な地方公共団体の取り組み事例
こうした奨学金返還支援の取り組みは地方公共団体が主体となって行うものであり、各地方公共団体が、地域の実情に応じ、多種多様な取り組みを実施している。若者の域内への定着のみならず、不足している特定分野の人材確保、域内企業の採用活動への支援等としても活用されている。上記①~③の分類に従って、いくつかの事例を紹介する。
- 東京都利島村では、利島村奨学資金貸付金の貸付期間終了後、貸付を受けた期間と同期間利島村に居住することで、全額を返還免除している。
- 佐賀県では、薬剤師免許取得後、一定期間(貸与期間の1.5倍)指定薬局で薬剤師として従事した場合、全額を返還免除している。
- 千葉県では、「教育不足解消に向けた奨学金返還緊急支援事業」を実施し、公立学校教員になることを強く希望する者のうち、教員採用選考に合格し、採用後11年間以上勤務予定の方を対象に、採用2年目から10年間県から直接日本学生支援機構へ支払いを行っている(上限307.2万円)。
- 和歌山県紀美野町では、町内に定住し、就業又は起業している30歳未満の方を対象に、町内勤務の場合は全額(年間上限24万円)、町外勤務の場合は半額(年間上限12万円)の補助を行っている。
- 宮城県では、就業員への奨学金返還支援を行っている県内のものづくり企業に対し、従業員への奨学金返還支援額の1/2を補助し、若手人材の確保等を支援している(補助上限額は複数のプランがあり、最大額は対象従業員一人当たり上限22万5千円/ 年、最長6年間)。
【5】今後の展望、高等教育機関への期待
総務省統計局が2025年1月に公表した『住民基本台帳人口移動報告2024年結果』によると、東京圏の日本人転入超過数は11万9337人(前年比4535人増加)となり、新型コロナ下での減少傾向が薄れ、転入超過数が増加している。若年層がその太宗を占めており、若年層の地方定着に向けた取り組みの強化が必要である。
地方公共団体による奨学金返還支援の取り組みは、令和6年現在、全ての都道府県と約5割の市区町村に広がっている。今後は、毎年度の調査を通じて、実施団体数のさらなる増加とともに、支援内容の充実を促し、若者の地方定着を促進していきたい。
また、地方公共団体の奨学金返還支援の促進とは別に、内閣官房新しい地方経済・生活環境創生本部事務局では、学生が卒業時に地方へUIJターンすることを促進するため、従来の移住支援事業に加えて、令和6(2024)年度より、「地方就職学生支援事業」を開始し、地方へ就職・移住する学生を経済的に支援している。具体的には、都内に本部がある大学の東京圏内のキャンパスに通う学生が、東京圏外の企業の採用活動(選考面接)等に参加するための交通費の最大2分の1を補助するとともに、実際に地方に移住する際にかかった引っ越し費用を支援している。また、令和7年度から、本制度の見直しを行い、
- 大学の学部生に加え、院生も対象
- 交通費と移転費の両方、またはいずれか片方でも申請が可能
- 交通費を支給の対象とする学生の就職活動等の期間は設定せず、インターン等の交通費についても申請可能
- 企業に加え、官公庁(※移住先地方公共団体が機関・職種を判断)や農林水産業等の家業に就職・就業する場合も申請が可能
本事業は、奨学金返還支援同様、地方公共団体が主体となって実施するものであり、支給の要件等については地方公共団体によって異なるため、詳細は移住先の地方公共団体にお問い合わせを頂きたい。
これらの取り組みにより、地方公共団体による高等教育費の負担軽減に向けた支援を促すとともに、若者の地方定着や卒業後に地方にUIJターンする学生の増加を目指していく所存であるが、高等教育機関においては、地方公共団体や国の取り組みを、学生に積極的に周知していただきたい。できるだけ多くの学生に、こうした支援制度を活用していただけると幸いである。
【印刷用記事】
【寄稿】地方公共団体による奨学金返還支援の取組等について/内閣官房新しい地方経済・生活環境創生本部事務局/ 内閣府地方創生推進室 参事官 塩田剛志
