【Interview】日本をもう一度元気に戻す教育的観点からの国家プロジェクト 中央教育審議会大学分科会高等教育の在り方に関する特別部会部会長・永田恭介氏(筑波大学長)に聞く

【PROFILE】永田恭介
1953年生まれ。1976年東京大学薬学部薬学科卒業。
1981年東京大学薬学系研究科博士課程修了。
国立遺伝学研究所助手、東京工業大学助教授を経て、
2001年筑波大学基礎医学系教授、2013年に筑波大学長就任。
2015年より中央教育審議会大学分科会会長、2017年より中央教育審議会副会長、
2019年より国立大学協会会長を歴任。
インタビュアー
リクルートカレッジマネジメント編集長 小林 浩
「我が国の『知の総和』向上の未来像 ~高等教育システムの再構築~(答申)」を公表した。
2018年に策定した「2040年に向けた高等教育のグランドデザイン(答申)」
(以下、グランドデザイン答申)に続き、2040年以降の急速に少子化が進行するなかでの
将来社会を見据えた高等教育の在り方について専門的な調査審議を行うため、
2023年10月に「高等教育の在り方に関する特別部会」(以下、特別部会)を設置し、
1年以上に及ぶ議論の結果を答申として取りまとめたものだ。
18歳人口の減少により、2040年の大学進学者数は46万人と27%の減少が見込まれるなか、
2040年以降の高等教育が目指すべき姿とは。
答申の背景にある課題意識、概要、大学の対応について、永田恭介部会長にお話を伺った。
【1】答申の背景にある課題認識
人口減でも一人ひとりの知のスペックを上げて日本を元気に
――今回の答申をまとめるにあたって、背景にはどんな課題認識があったのでしょうか。
もともとの危機感として、日本はビジネスも学問も停滞して元気がない、これをなんとかしたいというのが一番の発端でした。
直接の原因は経済の停滞です。『ジャパン・アズ・ナンバ-ワン』からアメリカが学んだのは、日本型のものづくりモデルにはもう勝てないということでした。そこから方向性を根本的に変えてデジタル産業に大きく舵を切った。日本はこれに遅れたわけです。
この遅れた理由が問題で、イノベーションを担う人がいないからです。我が国全体に高揚感がなく、リスクを冒してでも何かやろうという人がいない。やはり「人」なんだとなったときに、もう人が増えないという大変なことに気づき、これが原因に帰着するところです。どのくらい減るかというと、18歳人口が2040年には今より3割減り、2050年には半分にも減るのです。
実はグランドデザイン答申の時にも、「人の数×個々のスペック」のシグマが激減することには気づいていましたが、当時の社会認識がそこまで協調的ではありませんでした。私が特別部会の最後に「今回(知の総和答申)の仕上がりが、グランドデザイン答申のほぼ目的だった」と述べたのにはこういう背景があります。人の数が減少しても、一人ひとりの知のスペックを上げて、日本全体の知を維持、向上させようというのがこの答申の目的なのです。
――文科省の試算によると、入学定員300名ぐらいの中間的規模の大学が毎年90校ずつ減っていく計算になります。地域によっては空白地帯が出てくる可能性もあり、東京一極集中と地方の問題をどう考えていますか。
そのキーポイントは小学校廃校の頃からありました。町に小学校がなくなった途端、急速に過疎が進んだことから、小学校が果たしている役割は極めて大きいと思っていました。大学がなくなると同じことが起こるわけで、日本全体の地域分散をどう考えるべきか、どこまで進めていいか悩みました。
この点、アメリカはIT革命で分散化が進んでおり、テキサス州へ大手企業の本社移転が続く等、ニューヨークやロサンゼルスの本社が驚くほど減っています。
日本はというと不思議なほど東京が大好きなので、この体質はなかなか変わらないでしょうが、豊かに暮らす地域はあって当たり前なので、人が減っても地域はなんとか残したいと思いました。それには、高等教育機関が地域のアウトカムにつながる人材育成や科学技術の発展に寄与し、ビジネスとアカデミアが協働・集積することで、住める環境を作っていけばいいのです。協働なしに地方創生はない、今回の答申はその点を最優先事項としています。
――リクルートワークス研究所の試算によると、2040年には15歳から64歳の生産年齢人口が労働需要に対して1100万人不足するとされています。特にエッセンシャルワーカーと呼ばれる地域に必要な人材が不足する点についてはいかがですか。
トラック運転手の不足等、現場で働く人が減少する問題を解決する方法は、テクノロジーしかないというのは明らかです。既に自動運転バスも稼働していますが、地域にもテクノロジーを使いこなせる、あるいは作り出して地域にフィッティングできる人材が必要になります。だから地域と高等教育機関が一緒に育つという意味で方法は同じなんだと思います。
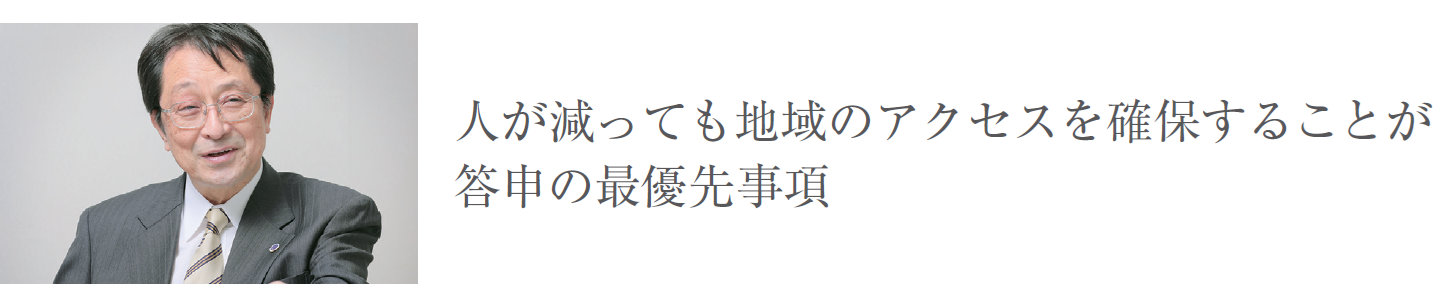
【2】答申の概要
「知の総和」向上を実現する3つの目的
――今回の答申の概要についてご教示ください。
本答申において、我が国の高等教育が目指す姿は「『知の総和(人数×能力)』の向上」です。それを実現するための高等教育政策の3つの目的として、①「質」の向上、②「規模」の適正化、③「アクセス」の確保を設定しています。
人口が縮小するなかで、高等教育全体の「規模」の適正化を図りつつ、それによって失われるおそれのある「アクセス」の確保策を講じるとともに、「規模」の縮小をカバーするだけの知の総和向上のために、教育研究の「質」を高めるという考え方です。
①「質」の向上
――質の向上が目指すところは何でしょうか。
知の総和を向上させるために、学生一人ひとりのスペックを上げなければいけないので、教育の質を変えなければいけません。これにはコンテンツで変える部分とシステムで変える部分の両方があります。
コンテンツでは、グランドデザイン答申の学修者本位の教育を一層推進し、主体的・自律的学修のための環境を構築します。
システムでは、従来から指摘のある労働生産性を改善するために、学士・修士5年一貫教育の大幅拡充を行います。人文・社会科学系なら修士課程、自然科学系なら博士課程を普通にします。
――教育の質を評価する新たな認証評価システムに変わることも大きな転換ですね。
これについては、第三者評価の対象を「機関別評価」から「学部・学科等別評価」に変え、教育の質を数段階で評価する方法に移行します。
高等教育機関がやるべきことは、まず1番目に教育の評価機軸を作ること、2番目にそれを認証評価に入れることです。新しい認証評価の役割は、各大学が目指す教育や研究を各自の指標に基づいて行い、ここまでのレベルの成果を出しますということを明示して、評価を受ける点です。評価する側も成果がレベルに準拠しているかを厳しく評価する。それができていなければ撤退するしかありません。
②「規模」の適正化
――規模については誤解が多いようですが、個別大学の規模ではなく、全体の規模を適正化するということですよね。
そうです。日本全体の知の総和に必要な人数を確保するために、高等教育全体の規模を適正化するということです。そのなかで、それぞれの規模を縮小するのか、あるいは残す大学を選択していくのかという問題になります。
今回は減少分を補うのに、留学生や社会人等の多様な学生の受け入れを促進します。ジェンダーバランスに偏りのある理工系への女子の進学も促進しますが、伸び悩む社会人教育も課題です。
留学生に対しては、日本の知の総和の向上のために日本に貢献してほしいわけですが、それには日本人のマインドチェンジが必要になります。病院やお店の英語対応を始め、日本で学んだ外国人が共に働き、暮らすことが幸せだと思えるような環境を作る必要があるのです。ただ留学生の数を取るという話ではなく、教育機関として日本社会に適合してもらうための覚悟をそろそろ持たなくてはいけません。
③「アクセス」の確保
――アクセスの確保ではどのようなことを目指していますか。
やはり地域をなんとかして守らないといけません。生まれた土地で学び、貢献したいという方のためにも、地域には適正な大学が配置されるべきです。奨学金や高等教育の修学支援新制度等、個人への経済的支援も不可欠になります。
特別部会で議論になったのは、国公私立という設置者別の特性を一律に考えられないという問題です。国公立大学は国や地域の牽引役の役割で全国の都道府県に分散していますが、私学は建学の精神と経営の観点で圧倒的に東京が多いので、やはり東京と地方は分けて考えるべきです。基本は情報公開を含めた努力で自由競争していただくとして、市場経済における自由競争に委ねていては成り立たない地域も出てきます。各都道府県にせめて1つか2つは知の拠点があるべきで、結局ここが一番の悩みでした。
そこで産業界、自治体、大学で、地域の志願動向や人材需要等を議論し、地域の将来像を作る協議体「地域構想推進プラットフォーム」(仮称)を構築し、協議体で議論した内容を大学間連携や産学官金連携で推進する「地域研究教育連携推進機構」(仮称)の構築を提言しました。
これを実効性あるものにするために、地域の自治体の中に専門の部署を作り、地域を維持・成長させるだけの人材総量と知の総和を計画するコーディネーターとなっていただきたいと考えています。それができれば国公私立の役割もおのずと決まっていくはずです。そしてこの実現のために、ぜひ文科省には地域創生の切り口で積極的に他省庁に働きかけていただきたいと思っています。

【3】大学の使命とは
大学人は学術による社会発展で地域に貢献するという自覚を
――部会の中で「これは国家プロジェクトの一環という意識を持って進めている」とおっしゃっていましたが、そういった内容が今回反映されているということですね。
そう思っています。地域分散や留学生の議論も含め、国家観を持って、我が国がどうなっていくべきかを真剣に議論しなければ中途半端なものになると考えていました。
だから今回は、国のグランドデザインにも近づきつつあることを、教育の観点から取り組もうとしています。これまでは定まった数の学生を優秀に育てて卒業させれば良かったかもしれませんが、今後はキャリアパスの先も大学が作らないといけないし、それを維持するためには地域の方々に理解してもらう必要があります。その自覚こそ、各大学の先生方に本気で持ってもらわなければいけません。
1947年の新制国立大学発足の時に、大学は学術の成果により社会の発展に寄与することとして各都道府県に配置されました※1。70年前から大学は地域社会に貢献するという使命を持っているのです。
社会貢献を念頭に置いた学問はダメだと思われる方もいるようですが、これについては日米で研究の動機を比較した調査※2があります。この中では研究プロジェクトの動機を、①基礎原理の追求、②現実の具体的な問題解決、③両方非常に重要、④両方重要でないの4象限で示しており、日米ともに最も高かったのは①基礎原理の追求(日本45%、米46%)でしたが、2番目に差異が出ました。米は③両方非常に重要(33%)だったのに対し、日本は④両方重要でない(25%)だったのです。真理探究もしないし社会にも貢献しないと回答した人が30%近くもいたことは衝撃的で、日本の大学は歴史の中で固有の進化を遂げてしまいました。もちろん地域と一緒に努力をされている大学も実際にありますが、学長は分かっていても隅々の教員まで本当に分かっているかというと、違う気がしています。
昨年2月には日本経済団体連合会が「博士人材と女性理工系人材の育成・活躍に向けた提言」を公表する等、産業界がイノベーションを起こす高度専門人材獲得に初めて真正面から取り組み、大学と連携・協働しようと意欲を示しています。大学と社会が共に理解を深める時期に来ているのです。
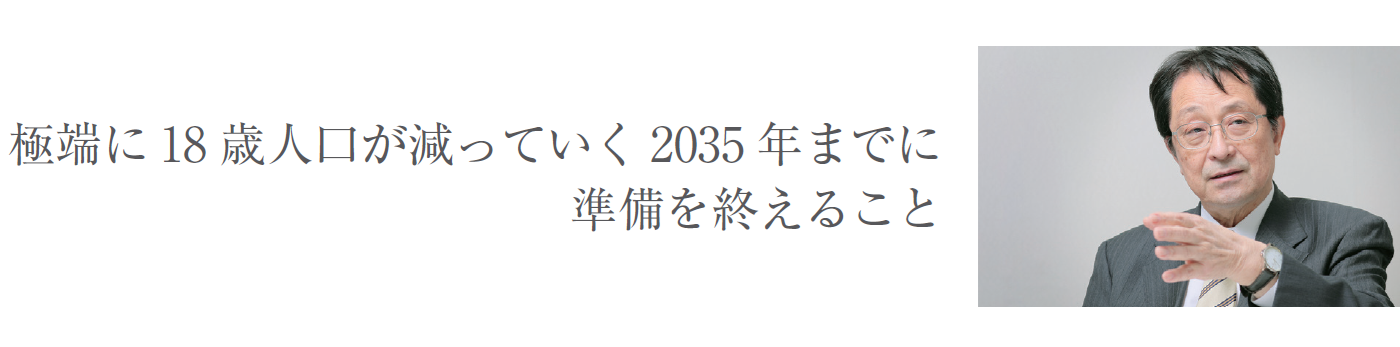
【4】大学の対応
2035年までに準備を終えないと間に合わなくなる
――18歳人口の減少は分かっていても、大学進学率の上昇で目の前の学生が減らないので、危機感が現実味を帯びていないように思われます。今後はどのようなスピード感で進めていくべきですか。
各大学は2035年までに最後の準備を終えることです。そこからは極端に18歳人口が減っていくので間に合わなくなります。来年から減るから入試や留学生の数を変えようとしても急には変わりません。入試を変えるには3、4年かかり、留学生をリクルートしようと急に外国へ行っても誰も相手にはしてくれません。
――2035年までに準備を終えておく必要があるのですね。
そうです。そこからは準備したものを実装化していくわけですから、今回はこのことを強く申し上げたいです。準備のないまま先に進むと、大学だけでなく地域社会や日本全体が衰退していくことになるので、危機感を強く持ってほしいと思います。
――答申を受けて、大学経営層が今後考えなければいけない点はどのようなことでしょうか。
もう今の1点に尽きます。本当の危機が到来してからでは間に合わないことがたくさんあるからです。入試やリクルート以外に、カリキュラム内容も変える必要があります。母数が減るので、これまで取らなかった層も獲得して育てようとすると、コンテンツが同じではついていけない学生が出てきます。こういうことを急にはできないから、徐々に準備していく必要があるのです。
野球に例えれば、正規分布で能力を分布させて、一握りの優れた選手だけで構成されたプロ野球を今私達は見ているとします。しかし山が小さくなり、一握りの幅に下手な人も入れなければ人数が集まらなくなると、「そんなプロ野球見たくない」となります。今後、全ての分野でこれが起こるので、我々大学人には学問分野でこれを回避する大きな責任があるのです。
――そうすると、各大学は自大学の定員規模をどう考えていったらいいでしょうか。
基本的には今の定員を維持することは不可能です。各大学のお考えがあるでしょうが、先ほどの学生の幅を広げる案に対して、ハイレベルを志向し、大学院にシフトして学内の定員を振り替える案も考えられます。
各大学に思いだしていただきたいのは、育てる人材という目標があって、そのためのアドミッションとカリキュラムなので、どこかが欠如する作り方をすれば失敗するということです。規模の問題は質とも繋げて考えていかなければいけません。経営のために何でもいいから人を集めてやることが、本当に我が国に資する大学なのかを考えてほしいと思います。
――最後に、部会長として総括メッセージをお願いします。
これからは奨学金で学生を獲得するより、どちらかといえば学費を上げて獲得する時代になります。自分達の教育の質の向上を不断にやっていただかないと、いずれ選ばれなくなります。序列やグループで物事を考えている場合ではないのです。
学生も自分がなりたいものになれるかどうかで大学を選んでほしいと思います。私の授業では「皆さんの仕事は学者、会社員、社長の3つしかない」と言っていて、学生には全員がベンチャーを起こすくらいの気概を持ってほしいし、それを教えられる大学に変わってほしいからです。
今回の答申はそういう意味で、エンタープライジングな気持ちを持って、この国をもう一度元気に戻すための国家的プロジェクトともいえるでしょう。
(文/能地泰代 撮影/平山 諭)
- 教育基本法、新制国立大学の設置に関する十一原則
- 科学技術政策研究所・一橋大学イノベーション研究センター・ジョージア工科大学一 「科学における知識生産プロセス:日米の科学者に対する大規模調査からの主要な発見事実」(2011年)
【印刷用記事】
【Interview】日本をもう一度元気に戻す教育的観点からの国家プロジェクト 中央教育審議会大学分科会高等教育の在り方に関する特別部会部会長・永田恭介氏(筑波大学長)に聞く
