【リカレント教育】聴覚障害者・視覚障害者への教育で研ぎ澄まされた「伝わる教育」の最先端/筑波技術大学
【主任研究員 現地レポート】リカレント教育の挑戦【5】
18歳の入学者を社会へと送り出すことに注力してきた日本の大学にとって「新規事業への挑戦」といえるリカレント教育。先行大学の事例を、学ぶ社会人の視点で現場からレポートしていく。【取材・文/乾 喜一郎 リクルート進学総研 主任研究員(社会人領域)】
手話通訳・文字通訳だけが「情報保障」じゃないー。提供されているのは「学修者本位の教育」そのもの
■筑波技術大学

◆筑波技術大学 天久保キャンパス(写真左)春日キャンパス(写真右)
1時間半の取材を終え、学内を案内いただいていた時のこと。ふと、今日は取材中いちども「聞き返す」ことをしていないことに気づく。
耳が良いほうではない筆者は、普段の取材時、うまく聞き取れなかった言葉を確認することが多い。日常会話ではいちいち聞き返して会話の流れを断ち切ることができず、あて推量で流してしまうこともしばしば。コロナ禍の折にはマスクのために声がこもってしまって大変でもあった。そのストレスが、今日は全くないのだ。
お話を伺ったのは筑波技術大学でリカレントプログラムを担当する河野純大教授。決して大きな声ではないのだが、一つひとつの音が明確で、口元の動きも大きい。そのためだろうか。
「聞こえない方、見えない方の教育を担う私達には、伝えるということについて、高いスキルが求められるのです」…取材中の河野氏の言葉が思い出された。
リカレントプログラム立ち上げは「学べる機会がない!」という卒業生の声から
筑波技術大学は聴覚障害者・視覚障害者を対象に設立された国立大学。つくば市内に二つのキャンパスを有し、聴覚障害者を対象とした産業技術学部、視覚障害者を対象とした保健科学部、双方を対象とした共生社会創成学部の3つの学部を持つ。共生社会創成学部は、当事者として社会にある壁を取り除いていく人材の養成を目的に、25年春に新設された新しい学部だ。
筑波技術大学の使命は、社会で活躍する聴覚障害者、視覚障害者を増やすこと。そのため創設以来、卒業生が活躍できる職域の開拓と、職場への定着に取り組んできた。各領域の教員がそれぞれ卒業生、およびその就職先の企業や施設とコミュニケーションをとり、何かトラブルが起こった際には、その会社に出向いて双方の言い分を聞き、トラブルを解決していく…そうやって卒業生を手厚くサポートしてきたのである。リカレント教育に取り組んでいるのも、「学びたいことがあるけれど学ぶ機会がない」「自分達がちゃんと学べる環境がない」という卒業生達の声に応えてのことだ。河野氏は自身の研究テーマが「遠隔での情報保障」だということもあり、研究チームの技術と知識を生かしてリカレントプログラムに携わってきた。
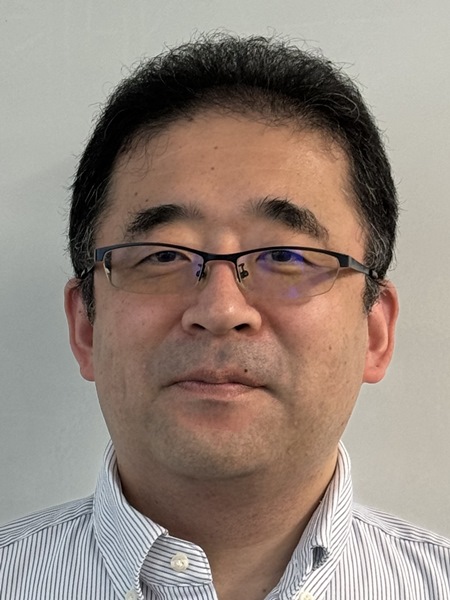
◆河野純大 氏
筑波技術大学 学長特命補佐(リカレント教育)
産業技術学部・共生社会創成学部 教授
情報保障とは、聴覚障害や視覚障害によって情報を収集することができない人に対し、文字や手話、音声などの代替手段を用いて情報を提供することをいう。全ての授業において聞こえない人・見えない人がしっかりと理解できるよう教育を提供してきた筑波技術大学は、この情報保障において、プロ中のプロといえるだろう。
「当初は東京などで貸会議室を借りて、教員が出向いて授業を行っていましたが、どうしても限界がある。それが、コロナ禍でオンラインが普及したことで、手話通訳や文字通訳がオンラインで手配できるようになった。おかげで、情報保障のある授業を提供できるようになったのです」(河野氏)。
ちょうど文部科学省の「就職・転職支援のための大学リカレント教育推進事業」があり応募。採択されたことで情報保障の費用を確保、2つのリカレントプログラムを立ち上げることができた。
視覚障害者を対象とするプログラムは、はり師・きゅう師、あん摩マッサージ指圧師、理学療法士の有資格者を対象に、最新の医療情報のキャッチアップや技術の向上を目的とした履修証明プログラム。オンデマンドの授業が中心となっており、補助期間終了後も継続中で、昨年度は約20名が履修証明書を取得した。一部のみの履修者も含むと、申込者の総数は約100名にのぼっている。
聴覚障害者を対象に2023年度に実施したプログラムは「D&I推進スキルアップコース」「DXスキルアップコース」の2種類の履修モデルを持つ。両モデル共通の科目としてコーチングやアサーティブコミュニケーション演習などのビジネススキル科目が、D&I推進スキルアップコースにはセルフアドボカシーや職場における交渉演習などの科目が、DXスキルアップコースにはVBA応用演習やデザイン思考演習などの科目が設けられた。どの科目も、リアルタイムで受講者同士がコミュニケーションしながら学ぶことが肝となっている。そのため情報保障のための費用負担が大きく、事業終了後は60時間まとめての開講はせず、単発の科目を実施している。
では、実際にどのように情報提供がなされているのだろうか。2025年6月28日、筑波技術大学「聴覚障害者のためのキャリアサポートセンター」が実施したオンラインイベント「聴覚障害のある社会人のための情報交換会」に陪席させてもらった。
同センターでは、聴覚障害者と聴覚障害者に関わる方々が充実したワークライフを過ごすことができるよう、年に数回、テーマを定めてこうしたイベントを実施している。今回のテーマは「職場でのコミュニケーション~会話のつまずきからみえてくること~」。当事者同士の語り合いにより、自らのコミュニケーションを振り返ったり、お互いでヒントを与えあったりすることが狙いである。
最初にイベント全体の構成や注意点が伝えられるのは通常のオンライン講座と同じ。しかし、zoomの画面が普段とは違っていることに気がついた。共有資料が大きく表示されていないのだ。
筆者のパソコン上では、zoomの画面は16のグリッドに分割されて表示されている。河野氏や本日の司会、ファシリテーターを務めるスタッフ、そして参加者の方々はカメラオンにしていて、それは変わらない。しかし、共有資料の画面はグリッドのうちの1つにすぎず、小さな表示のママだ。疑問に思ったその時、河野氏よりチャット上でその理由が説明された。「本日は参加者の皆さまに『マルチピンの許可』をしています。適宜、自分が見やすい画面をピン留めしてご覧ください」。共有資料の画面の両隣に、文字通訳、手話通訳のグリッドがある。参加者それぞれが、自分が見やすい画面を大きく表示して見れるようになっているのだ。そこで、私は共有資料のほか、話者、文字通訳の3つの画面にピン留めしてみた。そうした間も、文字通訳の画面では、黒い背景の上に白抜き文字がつぎつぎと表示され、文章が流れていく。
画面下側には、文字通訳・手話通訳の方々のグリッドがたくさん、カメラオフの状態で並んでいる。交替要員の方々だ。
取材の折同様、河野氏の声も、最初に話題提供されたセンターのスタッフ・松谷氏の声も非常に聞き取りやすい。話すリズムはゆっくりと一定していて、ひとまとまりの説明ごとに、文字通訳の文字が追い付いてくるのを待つための時間的空白がとられる。この空白の時間、不思議にイラつくことがない。ちょうど空白の時間が、話された内容の咀嚼の時間になっているからなのかもしれない。

◆イベント終了時に撮影された記念写真(一部ぼかし処理をしています)
大学時代に情報保障のある授業を受けてきた筑波技術大学の卒業生と異なり、一般からリカレントプログラムに参加された受講者からは、「ちゃんと分かる!」と感動の声が多く寄せられたという。「まずは、ちゃんと分かる、ということがポイントなんです。通常の企業研修などでは、何だか動画だけ見せられて、なんか声が流れているようだけれど聞き取れない…そんな状態が当たり前となっているのが実情ですから、こういったちゃんとサポートのある形で学べる機会が貴重なのです。その環境で、例えば障害者差別解消法の知識だったり、どんなふうに交渉していけばいいのか、という演習だったりという、当事者のための情報をしっかり理解することができる。そこは、本当に、ものすごく感激していただける。本来はそれぞれの会社の研修もちゃんと手話通訳がつくなどサポートがあるべきだと思いますが…まだまだそれが社会の現実です」(河野氏)。
伝えるスキルを追究することで実現する「学修者本位の教育」
「聞こえない方といっても色々いらっしゃいます。手話をメインに使われている方もいれば、補聴器や人工内耳で音をメインに聞きとり、口の動きで補完している方もいる。また、あまり知られていないのですが、手話といっても『日本語対応手話』と『日本手話』の2種類あります。講座の同時通訳においては講師のお話を追いかけていくことになりますので、多くの場合、日本語の論理構造に近い『日本語対応手話』をベースに、ところどころ日本手話の表現を用いてもらっています」(河野氏)。
DX関連など高度専門領域の場合は、また別の工夫も必要になる。「当然ですが、各種の専門領域にもともと精通しておられる通訳の方はあまりいらっしゃいません。そこで、講師の方には2週間前くらいまでに資料を用意していただいて、通訳の方に予習していただくのです。通訳は通訳のプロではあるけれど、内容のプロではありませんから。また、最新の内容だと手話の単語がまだできていないことも多く、その場合は『指文字』と呼ばれる50音やアルファベットをそのまま表す表現を用います。そうした準備も必要になるのです」(河野氏)。
こうした情報保障のための工夫は、視覚障害の方を対象にする場合も基本的に同様。「全てを言語化し、音声で伝えていかなければなりません。特に図表や画像については丁寧な表現が必要です。もちろんどうしても難しいときもある。過去には、受講者に人体模型を貸し出して、実際に触って確認してもらいながら進める、という取り組みをしたこともあります」(河野氏)。
ブレイクアウトルームが始まった。筆者が割り振られたグループのファシリテーターは河野氏。気づくと、河野氏も、参加者の方も、発言の冒頭に「河野です。○○については~」などと、自分がこれから話すことを宣言して発言している。大人数のオンライン会議では、誰が話者なのか分からず、発言者のアクティブなグリッドを探すのに手間取ることがあるな、と改めて気づかされた。
このグループは過去に参加した経験がある参加者が多いようだ。そのためか、どの方の話も聞きとりやすい。話されている内容がぐんぐんと頭に入ってくるように思える。

◆対面での講座で手話サポートを行う河野氏。
机上のタブレットで文字通訳を表示している。
「外部講師の方をお招きして、そこに手話通訳、文字通訳をつける。実はそれだけでは、ちゃんとした情報保障になりません。例えば文字が出るまでの間にはタイムラグがあります。べらべら早口で話し、どんどんスライドをめくっていくようでは、伝わるものも伝わらない。また、質問ありますか、と投げかけても、すぐには出てきません。皆さん文字で打っているから。そこをしっかり待たないといけない。時間に余裕を持たせなければならない。そこで、授業の内容をうまく絞り、削ったところは課題や発問で補う…そんな工夫が必要になるのです」(河野氏)
確かに、話される量としては通常の場合より少なくなってしまうかもしれない。しかし、受講者が受け取る量、理解する量と考えるとどうだろうか。咀嚼の時間があり、考える時間があるぶん、聞こえる人・見える人にとっても、むしろ情報保障のある授業のほうが、学べる量はより大きくなるのではないだろうか。筑波技術大学で追究されているのは、学修者にしっかり理解し、修得してもらうための技術なのである。そう考えると、リカレント教育に限らず、学修者本位の教育を進めていこうとする大学教育全般において、筑波技術大学の実践から学び取れることは非常に大きいだろう。
「本学としては、学びたいと思われるあらゆるものに対し、それがちゃんと伝わるためのサポートをつけていきたい。ですから今後、他の大学のプログラムにこちらが情報保障だけ提供して共同でやっていく、そんなプロジェクトを立ち上げていきたいと考え、準備を始めています。複数の教育機関が連携する効果は非常に大きいのではないか、そう考えているのです。
こちらの記事の読者は大学の方々だと聞きました。もし、こうした観点に課題意識や関心をお持ちの方がおいでであれば、ぜひお声がけいただきたいと思います」(河野氏)
