【Interview】通信制高校卒業生に聞いた「学びの中身と成果」
高校段階で通信課程で学んだ人に、その選択の経緯や通信制高校の学習内容、
高校における経験から得たこと等についてお話を伺った。
通信課程で培った「自ら考えて勉強を進める力」が、
大学の学びにおけるアドバンテージに
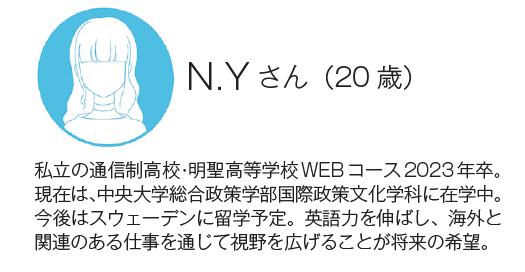
体調を回復するために通学から通信へ
中2の頃に体調を崩し、中学卒業後、単位制で時間の自由が利く昼間定時制の高校に一度は入学したものの、毎日通学することが難しくなりました。そこで、勉強して高等学校卒業程度認定試験を受けるか、通信制高校に入学するかという二つの選択肢で迷いましたが、高卒認定試験という選択は、どこの組織にも属さない状態になると思い、それを避けるため、高1の10月に通信制高校に編入しました。
その頃話題に上っていたN校をはじめとしていくつかの通信制高校を調べました。体調の問題があったので、スクーリング回数が少ないことを最優先に絞り、家族と相談して選びました。
授業は学校が開発したアプリから、指定の受講期間内に視聴可能な動画を見る形だったので自由に学べました。45分程度の動画を視聴した後、ミニテストを受け、一定の正答率をクリアできたら受講が認定されました。受講ペースは1日1講座視聴程度、内容も難しいものではなく、受講が億劫になることはありませんでした。私が通っていた高校のスクーリングは、体育の授業や定期テストのために年4回、4日間のみ。同学年の人達とはその日には顔を合わせましたが、仲良くなって連絡を取り合うといったことはありませんでした。
時間に対する自由度の高さ
通信制高校で学んで良かったのは、自由度が高く、普通の高校に比べ、自分で好きに使える時間が何倍もあることだと思います。やはり普通の高校だと、クラス単位での学習となるので、人によってペースが異なったり、自分が入試で使わない科目も勉強する必要がありますが、通信制高校は自分に合ったペースで効率よく時間を使うことができ、自分が本当にやりたいことだけできるのではないかと思います。私の場合は、大学受験のための勉強は独自で進める予定でしたし、それに加えてやはり体に負荷をかけずに体調回復に努めたいと考えていました。しっかり休む生活と、受験勉強、そして高校の学びを実現することが出来たと思います。
大学受験では、参考書やYouTubeの解説動画等を見ながら、独学で計画的にやっていました。現在通っている学部は、法律、経済、文化系と多様に学べる学部なのですが、進学時に「これがやりたい」ということは決まっていなかったので、幅広く学べるところが良いと考えて選びました。やりたいことが明確に決まっているなら通信制大学も良いとは思います。ただ、私の場合は様々なことをつまみ食いしてから本格的に学ぶことを決めたかったというのと、中学時代から同学年の人との関わりが5年ほどなかったので、社会に出る前に感覚を取り戻したくて通学制を考えていました。
こうした大学選びの際に学校側からの進路指導を受ける機会はありませんでしたが、通信制高校では先生方との関わりが希薄で、私の学習状況や性格について把握していないと考えていたため、特に指導を希望はしませんでした。
やるべきことに自ら取り組む姿勢と
多様な視点
通信制高校には、自ら目標を定めて、そこから逆算して、やるべきことに取り組んでいる人が少なくありません。また、通信制高校を選ぶ理由は人それぞれで、それが新たな視点を生むことがあると思います。似たバックグラウンドの人が集まる高校とは異なり、一つの物事に対し一人ひとりが違う見方を持っていることは通信制高校の強みかもしれません。
また、学力面を懸念する声もあるようですが、私自身、1年次にGPAが学科で1番となり、学部長賞を頂きました。大学では、自ら考えて勉強を進める必要がありますが、通信制高校では高校時代からそれができているので、それがアドバンテージになるのかもしれません。
通信制高校に行ったからこそ知った多様な学びの選択肢の存在
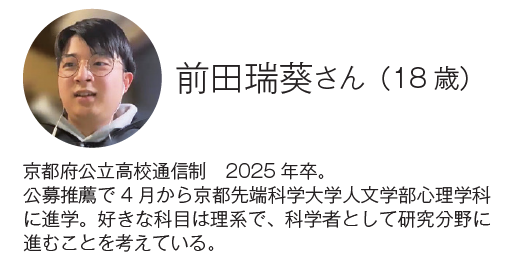
学費に加え「家から通える距離」であることを考慮
中高一貫のいわゆる進学校に通っていましたが、高校に上がって2週間ぐらいで通えなくなってしまい、辞めてしまいました。定時制高校には、期の途中からの編入ができず次の年度まで待たなくてはならないということで、結果として通信制という選択になったという感じでした。今の高校を選んだ一番の理由は、私立と比べて公立のほうが学費が安いという点です。公立の中でも家から通える距離にあるという点も考慮しました。
週に約1回× 5、6カ月の通学
時間の自由度が高い高校生活
授業は学校に通学してリアルで受講するという形。自宅で授業を受けるということは全くありませんでした。月曜と水曜の夜17:00〜21:00の間と、日曜日全日で行われていて、その中から自分が取りたい科目を選択して学びます。1科目につき所定のスクーリング時間を履修すれば、通学の必要はありません。
授業は、先生が黒板を使って解説するというスタイルで、理科の実験やPCを使った情報の授業等もありましたが、双方向コミュニケーションはほぼなかったですね。レベルは難しくなく、課題のレポートも一瞬で終わってしまう量でした。期初から9月か10月ぐらいまでの間、平均週1度の頻度で通学して授業を受け、あとはテストを受ければ卒業まで行ける、という感じでした。生徒の年齢層は20代くらいまでが多く、大人っぽい方もいた印象です。
高1の頃は8月に編入してからの半年はコンビニでアルバイトをしたりして過ごし、2、3年になってからは受験勉強として、スタディサプリの動画を見て自分で勉強していました。3年生のはじめに進路指導の冊子が自宅に送られてきて、一度は進路検討のためのホームルーム的なものに参加する機会はありましたが、大学に行くことは自分の中でしっかり決めていましたし、特に進路選択段階で学校の指導を頼りにするということはなかったと思います。
自分でキャンパスに足を運んでみて、落ちつけそうな場所があるか、毎日通えそうな環境か等、自分が実際に見て得た実感値に従って選びました。ネットの通信制大学も少し考えましたが、私の場合は見えない不安もあったので、選びませんでした。
11月頃に自己推薦で京都先端科学大学人文学部心理学科に合格しました。英語と情報の教育に力を入れていることがこの大学を選んだ理由。やりたいことが決まっていないので、将来何を目指すにしても英語と情報は最低限必要だと思ったからです。
多様な選択肢を持つことを知り得た通信制高校の場
通信制の良さを挙げるなら、やはり自分のペースで学べることだと思います。1、2カ月体調が悪くて休んでも、3年での卒業を諦めなくてもいいという点で気持ちに余裕が持てたと思います。
生徒同士の交流等、ある程度の高校生らしい生活も期待していたので、入学後には正直ギャップもありました。それでも3年間通信制高校に通ったのは、高校からある程度の課題を与えられて、それを解いて進めるというカリキュラムに沿った道筋を与えてもらえたこと。自分だけの力だったらだいぶ困っていたと思います。
また、学校のサポートとしては、3年の時に月に1回程度、スクールカウンセリングを活用して、悩んでいることを話せたのは良かったです。日常のふとした嫌な思いを話しながら、モヤモヤしたものがほぐれていったという感じです。
4月からは心理を学びますが、この先も視野を広く持って、違う分野を学んでみたり、大学院や海外に行く等、多様な選択肢を持っていたいです。そう思えるようになったのも、通信制高校で色々な人が学んでいるのを見たからこそ。かつては進学校行って偏差値の高い大学に入ることこそが正しい道だという考え方を良い意味で壊してくれたと思います。「道は一つじゃないんだ」と知ることができました。
