【座談会】専門学校にとっての機会と 経営に求められる視点とは
学校教育法改正等をきっかけとした柔軟かつダイナミックな改革が期待される今、
職業教育の価値がどう変わるのか、専門学校が果たすべき役割とは何か、
さらには専門学校が直面する課題とは何か、そして課題解決に向けてどのような取り組みを行っていくべきなのか―。
専門学校経営及び職業教育に関する有識者にお集まりいただき、様々な視点からお話を伺った。

【1】専門学校の価値はどう変わるのか?
日本において職業教育へのニーズは変わっていない
小林 少子化が進むなか、大学では様々な方策が検討されています。専門学校においても、その位置づけが今後どのように変わっていくのか問われています。また、今後の社会における職業教育の存在意義についても、議論が進んでいるところかと思います。
まずは堀さんから、JILPT(独立行政法人労働政策研究・研修機構)から見た、職業教育あるいは専門学校の位置づけをお聞かせください。
堀 職業教育の意義は、今も昔も変わらないと思います。変化してきたのは社会の評価だと捉えています。
専修学校制度が施行された1976年から1980年頃までは、職業教育の意義は社会で認識されていました。しかし、80年代の専門学校は、規模は拡大するものの、社会からの評価は今ほど高くありませんでした。その背景には、新卒一括採用した新入社員をトレーニングしていく、メンバーシップ型の日本型雇用があります。
その後バブルが崩壊し、大学の新設ラッシュ、入学定員の増加の一方で18歳人口は減少。入りやすくなった大学の進学率が高まるのに伴い、職業教育の価値が下がるのでは、と当時は予測されていたように思います。
しかし、90年代後半以降明らかになったのは、日本社会における職業教育のニーズの高さでした。「手に職をつけたい」という若者、あるいは保護者のニーズは明確にあり、今後もそれが続くであろうことが、ここ20年で示されています。
専門学校の存在意義の進化 4つの観点
小林 今お話しいただいた職業教育の価値、あるいは専門学校の価値について、多さんはどうお考えですか?
多 専修学校は制度が発足して50年の節目を迎えようとしています。この半世紀、時代の変遷とともに、社会のニーズが多様化あるいは高度化していくなかで、専門学校は実践的な職業教育の充実に努めながら、優秀な職業人材の継続的な育成、輩出に尽力し、社会に貢献してきました。
近年は第4次産業革命やSociety5.0の実現に向けて技術革新が進み、産業構造が大きく変化を遂げています。また、これに伴いグローバル化やボーダレス化も進み、国際競争が激化の一途を辿っています。加えて、少子高齢化が進み、生産年齢人口は減少。私達を取り巻く社会環境は大きな変革期を迎えています。
こうした環境下で、日本が持続的に発展していくには、様々な職業において、個々の能力や生産性の向上が必要不可欠であり、これに伴い、学び方や働き方も多様化していくでしょう。従来の単線型ではなく、「アカデミック・ライン」と「プロフェッショナル・ライン」という教育体系の複線化を確立し、多様な学びの選択肢を提供していくことが必要です。こうした動きに比例して、専門学校の存在価値もより進化していくでしょう。
その根拠を、4つの観点から示します。
第一に、「多様な学生の受け入れ」です。現在、高校新卒者以外にも大卒や社会人といった既卒者、昨今増加傾向の留学生等、多様な学生を受け入れています。
なかでも、社会人の学び直しの重要性は今後一層高まるでしょう。リカレント教育やリスキリング等、専門学校における実践的な職業教育を通じてスキルをアップデートし続けていくことは、これからの多様なキャリアに必須です。
また、優秀な留学生を計画的かつ積極的に受け入れて、地域を支える専門職人材に育て上げ、令和5年度から制度化された「外国人留学生キャリア形成促進プログラム」も有効的に活用しながら、就労につなげていかなければならないと思っています。
第二に「職業教育の充実」です。企業と密接に連携して教育を行う職業実践専門課程は、高等教育における職業教育のあり方を制度的に可視化し、産業界の要請に応え続けてきた、専門学校教育の本質であり、その充実が今後も期待されています。また、時々刻々と変化する社会や時代のニーズに即応した教育課程の編成や、今後あらゆる分野で必要とされるデジタルリテラシーへの対応等、柔軟かつ有効的な教育が、専門学校の強みだと思います。
そして第三に「専門職人材の継続的な輩出」です。専門学校は大学等と比較して、卒業後の地元での就職率が高い。成長分野に資する高度専門職人材から、地域を支えるエッセンシャルワーカーに至るまで、多様かつ必要な人材を輩出し、地域社会のインフラ維持に大きく貢献してきました。今後は産官学で、真に地域で必要とされる人材像と、その育成確保に向けた議論とを進化させていく必要があります。
最後に四点目として「国内外の通用性」です。今般の改正学校教育法では、高等教育機関として、大学との制度的な整合性を図るための様々な措置が講じられています。また、高等教育の資格の承認に関するアジア太平洋地域規約、いわゆる東京規約の中に専門学校が含まれたことや、国際標準教育分類(ISCED)のレベル6に高度専門士が位置づけられたこと等、専門学校が国内外において、高等教育として適切に扱われるようになってきたといえます。
こうした観点から、今後も専門学校は職業教育の要であり、存在価値はこれまで以上に高まっていくと考えます。
Keyword 職業実践専門課程
専門学校のうち、企業等と密接に連携して、最新の実務の知識・技術・技能を身につけられる実践的な職業教育に取り組む学科を文部科学大臣が「職業実践専門課程」として認定している。平成25年度から令和5年度までの認定等と合わせて、現在合計で1,110校(41.2%)、 3,199学科(44.6%) ※が「職業実践専門課程」として認定されている。
※:( )内の数字は学校数については全専門学校数(2,693校)、学科数については専門学校のうち修業年限2年以上の学科数(7,178学科)に占める割合。(専門学校数・学科数は令和5年度学校基本統計による。
- 企業等が参画する「教育課程編成委員会」を設置してカリキュラムを編成している
- 企業等と連携して、演習・実習等の授業を実施している
- 企業等と連携して、最新の実務や指導力を修得するための教員研修を実施している
- 企業等が参画して学校評価を実施している
- 学校のカリキュラムや教職員等についてHPで情報提供している
出典:文部科学省HP「職業実践専門課程」の広報資料および専門学校(専修学校専門課程)における「職業実践専門課程」の認定等(令和5年度)について より編集部作成
Keyword 国際標準教育分類 ISCED
学校教育におけるプログラムを、教育段階及び分野(普通または職業プログラム)ごとに整理し、各国間で比較可能とする分類。ユネスコ(国際連合教育科学文化機関)が決定する。
専門学校の高度専門士の位置付けについては、国内では、平成17年(2005年)以降、高度専門士の認定課程と同様の条件を満たし文部科学大臣の指定を受ければ大学院入学資格が認められる制度となっている。しかし、ISCEDにおいては、短期大学や2年制の専門学校と同じレベル5に位置付けられてきた。
高等教育の資格の承認に関するアジア太平洋地域規約(東京規約)の発効後6年が経過し、令和5年(2023年)には世界規約も発効した。こうしたことを踏まえ、高等教育の国際通用性を高めるなどの観点から、教育未来創造会議で取上げられ、当会議でも議論がなされた。これらを踏まえた文部科学省からの情報提供を経て、OECDが令和5年(2023年)6月に公開した“Education GPS”内の“Diagrams of education system”では、高度専門士がレベル6に位置付けられている。
(文部科学省「実践的な職業教育機関としての 専修学校の教育の質保証・向上と振興に向けて」より一部抜粋)【2】専門学校が選ばれている理由とは何か
学校種としての明確なアイデンティティ
小林 整理いただきありがとうございます。
では関口さんにお聞きします。「令和6年度 学校基本調査」では、大学進学者は増加、短大は減少、そして専門学校の進学率は前年度より2.1ポイント上昇し、過去最高の24.0%となりました。専門学校が学生から選ばれている結果だと思いますが、入学する学生の層はどのように変化していますか?
関口 新型コロナウイルス感染拡大によって減った留学生が、復活傾向にあります。専門学校の入学者が4000人増えたのは、海外留学生の影響だと考えられます。
50数万人という在学者数は、大学に次ぐ規模です。職業教育を行う学校種として、この規模を維持できていることこそが、専門学校の存在が社会から評価されている証左ではないでしょうか。
小林 国内外問わず専門学校が一定程度評価をされている理由を、関口さんはどう見られていますか?
関口 20〜30年前、「大学が全入時代を迎えるに伴い、大学と短大は増えて、専門学校は減少する」と予想されていました。対して私の見解は、「大学は増え、専門学校は維持。減るのは短期大学」というもので、現状その通りになっています。そう考えていた理由は、学校種としてのアイデンティティーにあります。
学問を学び、研究成果を出すというアイデンティティーを持つ大学に対して、専門学校も実利的な職業教育を提供し、就職につなぐという学校種としてのアイデンティティーを確立してきました。学校種としてのアイデンティティーが明確であれば、長期的に衰退することはないと、当時から考えていたのです。
その後、個々の専門学校、全国専修学校各種学校総連合会等団体が努力をし、実績を積み上げてきた結果、50数万人という規模が維持できていると考えます。
小林 関口さんの理論は、冒頭の「大学進学率が高まり、専門学校は衰退すると考えられていたが、実際は職業教育の根強いニーズが社会にあった」という堀さんの話に通じますね。堀さんは、なぜ大学一辺倒にならなかったと見ていますか?
堀 関口さんが、専門学校は「アイデンティティーが明確だ」とお話しされたように、高校生が全員「大学に行きたい」わけではないんですよね。高校生の学びのニーズは多様であり、かつそれに素早く対応できたから、専門学校は生き残ってこられたと考えます。
まだ世に出ていない新しいニーズを先取りし、カリキュラム化できるのが専門学校の魅力。さらに、それがフレキシブルであるという点が、大学に勝る専門学校の強さだと考えます。時代の流れとともに変化する、消費者のニーズや社会のニーズに即応して、教育をアップデートしていく専門学校の実践性が、社会から評価されているのではないでしょうか。
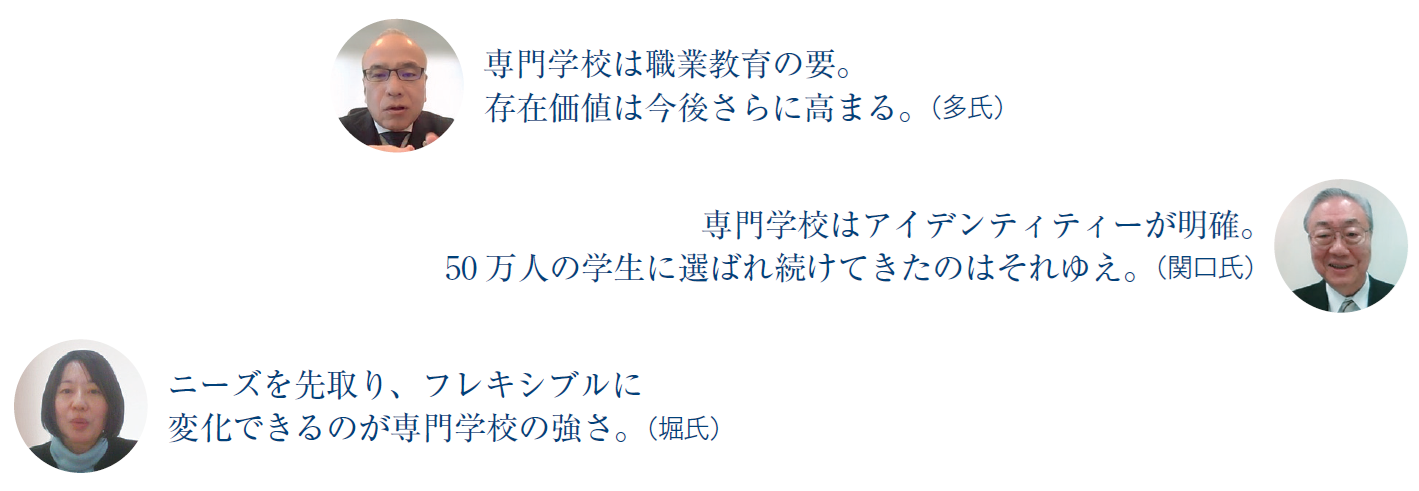
【3】分野や学び方へのニーズの変化は
全分野に必要なデジタルリテラシーを涵養する
小林 急速に変化する社会のニーズに即し、学校や学科、コースが柔軟に設計できる制度的なメリットが専門学校にはあるというお話でした。
では多さん、今はどの分野のニーズが高いのでしょうか?
多 やはりAI、DX、ICT等 デジタルに関係した学科、工業分野が伸びていくと思われます。
一方、これからの時代において、デジタルのリテラシーは工業分野だけに限った話ではなく、専門学校の8分野(工業、農業、医療、衛生、教育・社会福祉、商業実務、服飾・家政、文化・教養)全てに必要となる汎用的な能力です。全分野で育成する必要があります。
専門学校で4年間学ぶニーズが高まる理由
関口 「長期化」ニーズも高まっています。4年制の高度専門士課程が、留学生も含めて選ばれています。修業期間が長くなる分、学費は高くなりますが、より本格的で高度な教育を受けられるならば行かせようと考える保護者は増加傾向にあると感じます。
小林 どういう人が、何を求めて4年制で学ぶのでしょうか?
関口 例えば、私が学校長を務める東京スポーツ・レクリエーション専門学校には、スポーツアナリスト等を目指す4年制のスポーツ科学科があります。スポーツ科学を学べる大学がある中で、専門学校が選ばれる理由は、1年次から徹底的な実習授業を、プロ仕様の機材や施設を使って受けられるからです。社会に出て実際に求められる高度なスキル習得を、実践教育で実現するのが4年制なのです。
留学生にとっても、学位に限らず、技術を修めた証明となるディプロマ(高度専門士)は魅力のようで、多くの専門学校において、アジアの留学生を中心に、求心力となっています。
多 専門学校の修業年限は圧倒的に2年制が多い。ただ、1年生の後半から就職活動が始まるため、実践的、専門的な学びの期間にはかなり制約があります。
今は「長く、専門的で実践的な学びを受けたい」人が多く、高度専門士課程で学びを深め、より高い目標を持って就職したいというニーズを感じます。実際、2年制より4年制のほうが学生募集も好調です。
小林 「専門学校でも、大学に対抗してレイトスペシャライゼーションを実施し始めた」と一部で言われていますが、そうではないということですね。
社会に求められる職業の高度化、専門性の高まりを感じます。労働市場ではどうでしょう?
堀 特にIT系の分野等では、高度なスキルを身につけた職業人材のニーズは急激に高まっており、大学で情報について専門的に学んだ人材だけでは採用人数は充足しません。大卒に限らず、採用ニーズは高まっていると思います。
新たな分野・分類と職業教育体系の確立を検討
小林 先ほどお話に出た、専門学校の8分野について伺います。専門学校の実態が見えづらい原因の一つにこの分類があると感じるのですが、職業実践専門課程中心に情報公開が進められるなか、どのように捉えていらっしゃいますか?
関口 職業実践専門課程に限定したものですが、東京都専修学校各種学校協会で、新たな分野・分類を提案しようと議論中です。これに取り組む目的は、職業教育体系の確立です。
専門学校が社会から信頼を得るためには、職業教育体系が高等教育機関、あるいはさらに広い範囲で国際通用性を持った形で制度として認められる必要があるからです。
混乱を少なくするため、現8分野をさらに細分化する方向性で、検討していきたいと考えています。
小林 関連して、学位・資格を整理・可視化するNQF(National Qualifications Framework・国家学位資格枠組み)の構築について、堀さんはどうお考えですか。
堀 NQFの確立は、外国人労働者の受け入れを円滑にするとして労働政策においてもニーズが高まっています。資格の名称は国によって異なりますが、NQFがあれば外国で取得した資格の水準や難易度が可視化されるので、評価や比較がしやすく、国を越えた人材の移動をスムーズにします。ぜひ日本でも確立されることを期待しています。
<※2025年1月28日の大学分科会に「日本の学位・称号等枠組み(案)」が文科省より提出された。>
日本の大学の学位は比較的分かりやすいのですが、専門学校の高度専門士がディプロマに位置づけられた意義は大きいですね。ディプロマがあれば海外でも高度人材として処遇され、日本で在留資格を持って働くことも可能になりますから。
Keyword National Qualifications Framework(NQF)
概要
- 各国内の学位・資格などのqualifications 情報を一元的に整理し、可視化を図る参照ツール
- 各国の異なる学位・資格の読みやすさ(readablity)
- 比較可能性(comparability) を高めるための翻訳装置
- これまで別々に制度づけられてきた多様な教育訓練セクター間の関係を明らかにし、各セクターで獲得される資格に対してアウトカムや水準を設定
NQFに期待される役割
- 学位・資格制度の整理・可視化
- アウトカムに基づく資格の透明性の向上
- 学習者のセクター間移動(入学、編入学、就職など)の支援
- 教育プログラムの質保証システム(大学評価など)の一環
- 教育訓練と労働市場との関係性の強化
- 水準やアウトカムの策定に関する雇用者の関与
- リカレント教育・生涯学習・継続教育の促進
- 職業教育の地位の向上
https://doi.org/10.1108/HEED-05-2022-0019
(出典:文部科学省大学分科会高等教育の在り方に関する特別部会(第7回)配付資料)
【4】法改正は、専門学校にどのような影響を与えるか
自己点検評価義務化、単位制への移行、専攻科の設置、外部評価の努力義務
小林 ところで、学校教育法が一部改正されます。専門学校の何が変わるのか、教えてください。
関口 まず、大学との制度的な整合性を高める措置として、最低限必要な授業時間数という専門学校の履修制度を、大学と同じ「単位制」にします。単位制となることで、専門学校での学修成果を卒業要件として明確化できます。これは、国際通用性の点からも大きな意味を持ちます。
次に、「専門課程の在籍者の呼称の変更」です。現状の「生徒」から、高校を卒業して入学する専門課程については、大学同様に「学生」に改めます。
そして、今回制度化される特定専門課程(2年以上、62単位以上、の専門課程)は大学編入学資格及び専門士の称号が付与されることに加えて、1年以上の専攻科を設置することが可能となりました。また、その中で一定の要件を満たした「適格専攻科」の修了者については大学院入学資格及び高度専門士の称号が付与されることになります。
最後に「学校評価」です。教育の質の保証を図るための措置として、自己点検評価の義務化と同時に、「外部の識見を有する者による評価」いわゆる第三者評価を、努力義務化することになりました(一部義務化も検討)。
外部評価の努力義務化による専門学校への様々な影響
小林 専門学校にとって大きな転換期になると思いますが、約2800校ある専門学校全てで、対応は順調に進んでいるといえるのでしょうか。
多 ご指摘の通り、学校数が多いので、外部評価や単位制の変更等にどのくらいの学校が対応し得るのか、検討していく必要があるでしょう。2026年度の施行に向けて、「外部評価の努力義務化」が今後どう展開され、どんな影響があるか注視が必要です。
周知の通り、昨今は専門学校の様々な制度に対し、外部評価への取り組みが求められています。例えば、外国人留学生のキャリア形成促進プログラムの認定校や、適格専攻科の設置校等に対して、優先的に外部評価が義務化される見込みだと捉えています。適格専攻科の修了者と同様に、大学院の入学資格が付与されている高度専門士についても、理論上、義務化は避けられないでしょう。また、職業実践専門課程も、将来的には外部評価の導入が想定されます。文部科学省では、学校評価のガイドラインの改正、評価の対象や開始時期、さらには実施体制についての検討が進むでしょう。
こうした状況を踏まえ、全専各連では、全国の専門学校が外部評価を受審することになった際の課題を整理しています。外部の識見を有する者と、現在の独立した専門の評価機関における評価の質について同等性を求めていかなければいけません。あるいは、外部評価を受ける学校側の負担の軽減やメリット、つまり社会的評価や、補助金等のインセンティブのあり方、更には地域性や学校の規模を踏まえた外部評価への取り組み方に等ついて、議論を展開していきたいです。
また、「履修主義から修得主義へ」の転換、即ち「何ができるようになったか」という学修成果に対して単位を付与する「単位制の導入」は、制度の整合性という点では理解するものの、大学における制度の長所が、専門学校にそのまま生きるかは疑問です。必修科目に加えて、知識の幅や、見聞を広めるための選択科目がある大学とは異なり、専門学校は特定の職業に就くために学ぶので、ほとんどの授業が必修科目です。専門学校で学ぶ学生にとって、単位制の導入が有益なものになるように、教育課程の編成やカリキュラムの作成において、細心の留意が必要だと考えます。
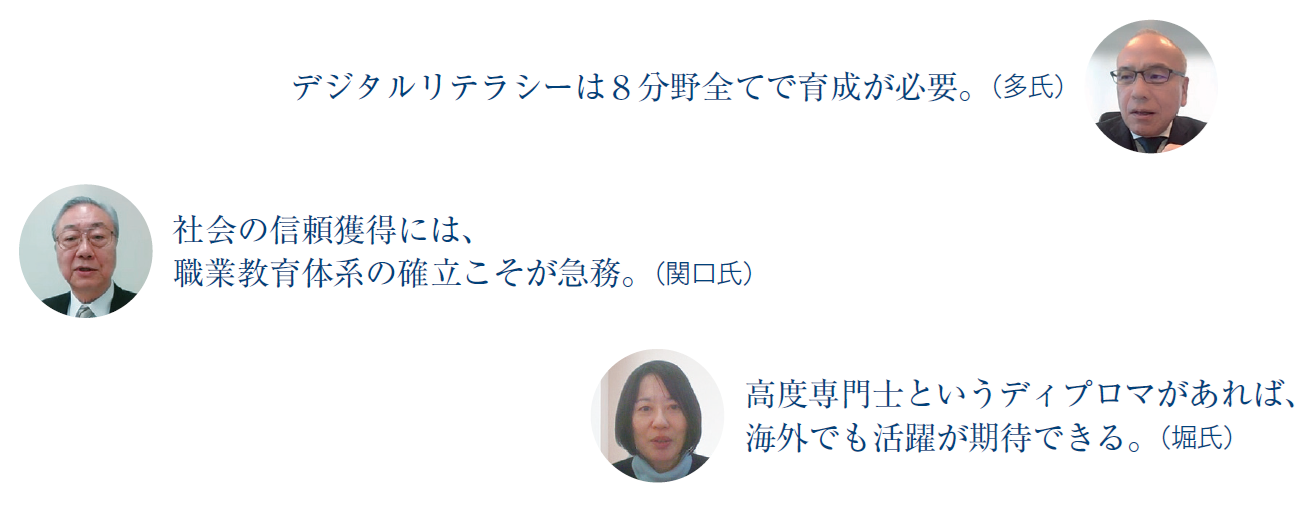
【5】専門学校が直面する課題と解決の方向性
職業実践専門課程の認定校が取り組みのモデルに
小林 今挙げていただいた点も踏まえ、今後、専門学校が直面する問題や、取り組まなければいけない課題とは何でしょう?
関口 専門学校を今後さらに良いものにしていくために、まずは職業教育の質を高めてきた職業実践専門課程の認定校がモデル的な取り組みを実践して、それをほかの学校に参考にしてもらうのが良いと考えます。
とはいえ、企業との連携という点においては、職業実践専門課程も課題があるので、より実践的で高度な成果を上げる必要があるでしょう。
その実現には、職業実践専門課程の認定要件を分野ごとの事情に即して変更したり、手薄である教員のマネジメントに関わる部分を強化したりする等、認定要件の改善も必要だと考えます。
1110校の職業実践専門課程の認定を有する学校が、職業教育のマネジメントを高めて、認定要件に厳密であることが、専門学校の質の保証において重要であり、最大の課題であると考えます。
多 学校経営の健全化に向けては、学校法人としての方向性や目標を明確に掲げることと、その達成に向けて必要なヒト・モノ・カネといったリソースの計画的な確保に向けて、中期的な事業計画を策定し、その実施に臨んでいくことが肝要だと思っています。教育の質の保証・向上と、中期事業計画の策定・実施、双方の取り組みを通じて、職業教育のマネジメントを確立して、 PDCAのサイクルを回しながら継続的な改善に努めていくことが、今一番我々に求められていることだと思います。
それから、専修学校の制度の複雑さの解消も大きな課題だと捉えています。専修学校制度が発足してから現在に至るまで、様々な認定制度が積み上がってきました。柔軟であるがゆえに複雑になり、結果、社会的認知や理解が進まないという状況を招いています。
専修学校という一つの学校種の中に専門課程、高等課程、一般課程と、課程が3つあること等、課程も制度も複雑であることは、学生募集やひいては学校運営にも直接的な影響を及ぼしかねません。この複雑さを解消していけるかも、今後の課題です。
関口 学校教育法で制度的な整備をして、なるべく専門学校としての全体性を担保する動きも肯定しつつ、一方で中核となる職業実践専門課程を優良化しようとすればするほど、それ以外の学校との間に乖離が生まれてしまう。矛盾をはらんではいるのです。ただ大切なのは、どちらの道に進むかを各学校が明確にしていくことだと思います。
各都道府県の専各協会やリーダー校が地域貢献を推進
小林 労働人口が減っていくなか、地域における人材育成についても期待が高まっています。専門学校の地域貢献のあり方について、関口さんはどうお考えでしょうか。
関口 地域貢献は、専門学校の重要なテーマです。高等教育の地域貢献といえば、自治体は大学に目線が行きがちですが、社会人の学び直しも含めて、専門学校が地域貢献に果たせる価値を伝えていかなければなりません。
そのためには、各都道府県の専各協会が、各地域の学校や産業のデータを収集し、地域が求める人材育成に活用できる状態を目指すと同時に、地域社会との関係性構築に努めていく必要があるでしょう。
さらに、そういった取り組みを、各地域のリーダーとなる専門学校が推進していくことも重要です。
小林 堀さんは、地域の労働市場における専門学校の役割や期待について、どうお考えですか?
堀 地元貢献は、専門学校が担う重要な役割です。地域によっては、大学を補完する役割を果たしている専門学校もあります。学びたい分野や専攻が、専門学校でしか学べないというケースで、今後も増えていくと予測します。専門学校には、大学にはない強みを生かしたポジショニングを期待します。
小林 全専各連としては、どう考えますか?
多 地元の専門学校を卒業して就職した人は、平均68%という高い割合で同じ都道府県内の企業に就職します。人材不足が深刻化の一途を辿る地域企業の振興は、専門学校の存続が生命線だと言っても過言ではありません。専門学校は地域の活性化の責務の一端を担っていると考えます。
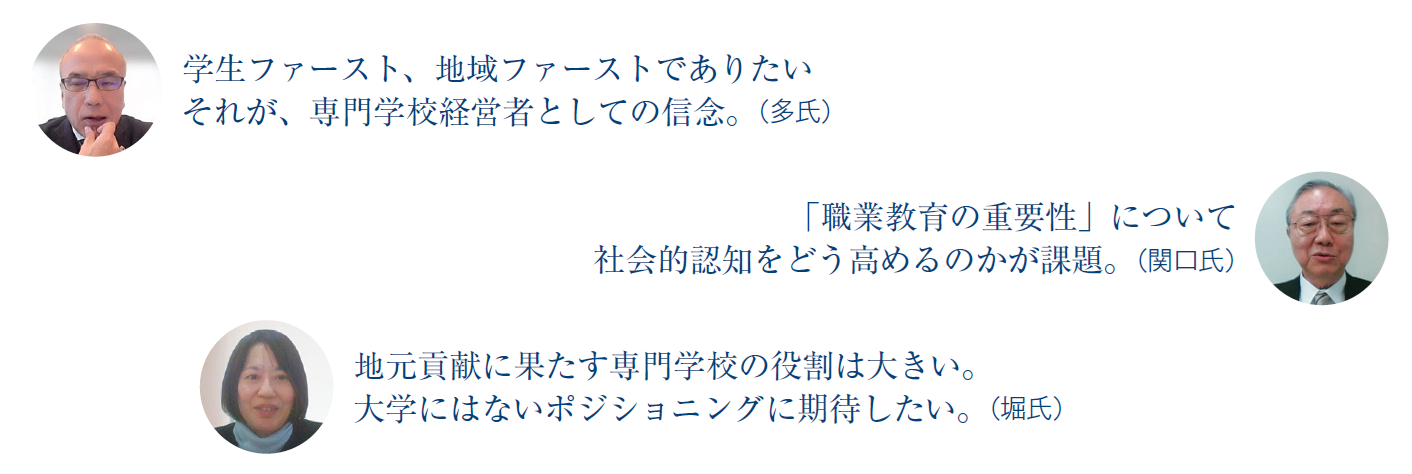
【6】将来に向けた専門学校の意義と期待
高等教育における、職業教育の唯一無二の存在に
小林 まとめに入りたいと思います。堀さんは、様々な高等教育会議に参加され、職業教育や専門学校、大学を見ていらっしゃいます。今後の専門学校への期待をお聞かせください。
堀 かつて、専門学校や職業教育について理解があまり進んでいなかった時代においては、専門学校の素晴らしさや特長を積極的に世に伝えることが重要でした。しかし現在は、職業教育や専門学校に対する社会の理解は浸透してきていると感じます。
目標とする職業に就くには、専門学校でしか学べないというケースや、地元に残りたいから専門学校進学を選択するという高校生も今後増えていくと思います。高等教育の中の一校種として、十分に重要性を認識され、明確に位置付けられた存在となってきたので、アピールのスタンスを若干変化させていくことも、今後のあり方の一つではないでしょうか。
関口 私も同感で、「専門学校」の存在を強調するというよりは、「職業教育の重要性」について社会的認知をどう高めるのかを、政策的な課題として捉えてもらいたいです。そうすればおのずと、職業教育の主役として専門学校が認知される。そういう社会へのアプローチが良いと思います。
多 50年の歴史の中で、先人の尽力によって、専門学校の存在価値は高まってきました。そして今、学校教育法改正もあり、制度的にも、従前と比べて存在感を示せるようになってきました。この先さらに存在感を高めていくには、職業教育の唯一無二の要になることが重要です。
大学全入時代といわれて久しいなか、「とりあえず大学へ行く」という風潮には流されない新卒者、あるいは様々な経験を経て、学び直しにチャレンジする既卒者、加えて、勇気と希望を胸に海を渡ってきてくれる留学生等、多様な学生が毎年専門学校には入学してきます。その学生達が専門学校に期待するのは、質の高い実践的な教育と安心して学べる学習環境です。
その期待に応えるべく、少子化の時代だからこそ一人ひとりの学生を大切にし、学生ファーストや地域ファーストの信念を持って、教育の質保証・向上や学校経営の健全化に努めていくことが、私達専門学校を経営する者の第一義だと考えます。
小林 まさに今、専門学校の役割も期待も大きく変わろうとしていることが良く分かりました。ありがとうございました。

(文/武田尚子)
【印刷用記事】
【座談会】専門学校にとっての機会と 経営に求められる視点とは
